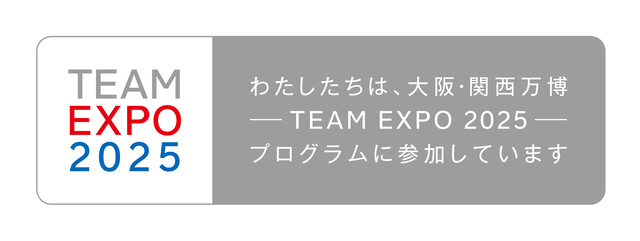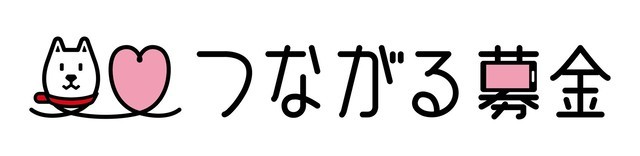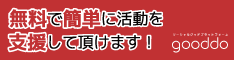動物愛護法改正PT
(1-2)強行規定について5/27開催の第10回PTでの課題への回答【環境省より】
自治体から動物取扱業者への指導等状況について
1.指導等の件数
・動物取扱業者を監督する67の自治体(47都道府県と20指定都市)に確認をとった。
・9割程度の自治体で、管内に飼養管理基準違反の事業所が確認されている。
| 第一種動物取扱業者 | 第二種動物取扱業者 | |
|---|---|---|
| 登録された事業所 | 700~800 | 20~30 |
| 立入検査が行われた事業所(年間) | 200~400 | 6~9 |
| 報告徴収が行われた事業所 | 自治体において概ね未集計 | |
| 飼養管理基準違反が確認された事業所(年間) | 自治体において概ね未集計 ※口頭指導件数と一致する自治体あり | |
| 口頭指導件数(年間) | 140~150 | 2~5 |
| 文書指導件数(年間) | 30~50 | 0.6~1 |
| 勧告件数(年間) | 0.1~0.3 | 0 |
| 措置命令件数(年間) | 0~0.04 | 0 |
| 業務停止命令件数(年間) | 0~0.02 | 0 |
| 登録取消命令件数(年間) | 0.01~0.06 | 0 |
※事務提要及び自治体回答(全項目又は一部項目に未回答の自治体あり)に基づく。
※年度によって事業所数・件数が異なるため、幅をもった記載としている。
・口頭や文書指導の事案で最多の違反内容は、飼養施設の管理・設備等(飼養管理基準第2条第1号又は第3条第1号)=ケージサイズ基準違反。犬猫については数値基準で現場を見れば一目瞭然なので、口頭などでの指導が一番多く行われていた。
・法に基づく措置として勧告や措置命令が行われた事案では、ケージサイズ基準違反に加え、ネグレクトにつながると想定されるような清掃・消毒の不足、人手が足りない員数規定の違反、獣医師の診療を受けさせない健康管理の不備等が相当程度あった。動物の健康に影響を及ぼすものは重大な事案なので、より重たい措置を執行している。
2.口頭・文書指導に従わない事業者への対応について
(1)複数回の口頭・文書指導に従わない事業者(55自治体回答)
55自治体のうち38自治体で、口頭・文書指導を複数回行ってもなお飼養管理基準違反が改善しない事業者が確認されていた。その事業者数は、うち24自治体で1~10件程度、14自治体で10超~100件程度。複数回の指導を行ってもなお違反を改善しない事業者は複数いる。
(2)当該事業者への勧告実施状況(43自治体回答)
複数回の口頭・文書指導に従わない事業者に対して、32自治体で、勧告は実施されていない。一方、7自治体で1~10%、3自治体で10~50%前後、某自治体では従わない事業者に対して100%勧告を行っていると回答があった。
(3)勧告を行う基準等(59自治体回答)
17自治体のうちほとんどの自治体で、複数回の指導に従わない場合には勧告等の実施や検討が規定されている(その他、基準を大きく逸脱している場合、勧告の必要がある場合等)。
一方、42自治体で、勧告を行う基準が定まっていない。
(4)勧告を行うにあたっての懸念(複数回答あり)(61自治体回答)
勧告の数が少ないというご指摘がある中で、自治体がどういう懸念があって勧告しないのか、勧告しにくいのかを確認した。
- 勧告すべきか否かの判断基準が不明確:54自治体(うち、最大の課題:26自治体)
- 違反であるか否かの判断基準が不明確:37自治体(うち、最大の課題:10自治体)
- 人員不足:35自治体(うち、最大の課題:11自治体)
- 前例がない:29自治体(うち、最大の課題:3自治体)
- 訴訟リスク:28自治体(うち、最大の課題:2自治体)
- 心理的負担:17自治体(うち、最大の課題:0自治体)
なお、5自治体では「勧告に当たる事業者がいない」「口頭・文書指導により飼養管理基準違反が改善されている」という回答もあった。
違反はわかっているが、そのうえでなお勧告するべきかどうかが分からない自治体が多い。
訴訟リスクは命令等を行う場合を想定(※勧告:行政処分ではなく行政指導で強制力なし)。
(5)勧告を行うにあたっての懸念への対応(59自治体回答)
自治体からは今後、以下の措置を導入してほしいという意見があった。
- 判断基準や手順等に係る環境省の技術的助言:54自治体(うち最も望ましい:32自治体)
- 他自治体における勧告事例等の情報共有:52自治体(うち、最も望ましい:7自治体)
- 人員増加(人件費増加含む):40自治体(うち、最も望ましい:12自治体)
- 警察に援助要請できる規定:37自治体(うち、最も望ましい:5自治体)
- 訴訟リスクに係る環境省の技術的助言:35自治体(うち、最も望ましい:0自治体)
- 1事業者に対して複数職員での対応:23自治体(うち、最も望ましい:0自治体)
- その他(行政手続法に係る研修等):5自治体
(2)意見交換
・(牧原議員)大阪府環境農林水産部から要望資料をいただいたので紹介します。
①虐待が疑われる動物の緊急保護
| 課題 | 府の対応 | 要望 |
|---|---|---|
・動物の健康と安全が脅かされる事態が生じても、飼い主が同意しない限り、動物の保護ができない など | ・行政からの放棄に応じない場合、所有者との交渉~放棄後の動物の保護を協力団体へ依頼する制度を構築 など | 法整備、罰則強化 要件を明確化したうえで、 ・行政が緊急保護できるよう 所有者の権利を制限する法、制度の整備、財政支援など |
②迅速な立入調査の実施
| 課題 | 府の対応 | 要望 |
|---|---|---|
・強制力のない立入調査のため、飼い主の同意がないと実施までに時間がかかる | ・抜き打ちを含む立入調査の実施(拒否時の罰則明示) ・対応マニュアル作成 など | 立入調査の強化 ・円滑な実施のため、警察官の援助が得られる法整備 |
③具体的な環境基準の設定
| 課題 | 府の対応 | 要望 |
|---|---|---|
・犬猫の健康が損なわれる臭気などの客観的な指標がなく、指導に限界 | ・立入検査時の臭気・温度・湿度の実態や飼養環境の把握など | 具体的な環境基準の設定 ・環境要因が与える影響について研究、具体的基準の設定 |
④動物取扱業者への規制強化
| 課題 | 府の対応 | 要望 |
|---|---|---|
・全国的に法違反疑いの事業者が後を絶たないが、業務停止や登録取消しまでに一定期間を要する | ・不適切な事業者への厳格な対処 ・責任者要件が厳格化された改正法の遵守の徹底 | 動物取扱業者の即時業務停止処分 ・基準違反の動取業者に、即時業務停止処分を科す法整備 |
・(太田記者)前々回PTに参加された新潟市動物愛護センター登坂所長からのご意見を紹介。「『~の場合には勧告しなければならない』という規定だと自治体としてはやりやすい。具体的にどうだったら何をするのかしっかり決めていただけるとよい。飼養管理基準省令の条項に評価の濃淡をつけたうえで、一部の条項については違反していれば勧告しなければならないといった定め方なら自治体判断がしやすい。」
・(福島議員)外国人技能実習制度の管理団体は許認可の取消しを結構していて、他の制度と比べてなぜ動物愛護は取消しまでいかないのか。勧告しやすくする必要があるのではないか。
⇒(環境省)「この違反のこの程度では勧告しない」というやり方より「例え小さな違反であっても改善しないのであれば勧告する」という流れの方が分かりやすい。この回答結果を見ても、そこが自治体でまだ十分に対応できていないところ。
・(日本動物福祉協会 町屋様)「複数回の指導」はどのくらいの期間で行われた回数なのか。この「期間」が「回数」以上に大切。
警察への協力要請は必要だが、反対に警察から協力要請があったときに断る自治体が多い。相互に協力体制がとれる形にしなければならない。
また、法制局の回答で「行政指導や立入検査から勧告等まで期限を区切っている法令はなかった」とあったが、児童虐待の48時間ルールは、通知等に当たるのか。そういった虐待への対応は法令には明記がないが、管轄の省庁が通知を出すということはあるのか。
⇒(法制局)児童虐待はおそらくなにか通知だと思う。行政指導や立入検査の結果どうするかはその時点では分からないので「この期間で勧告しなさい」とするのは、どのように行政内部で検討するかも含めてなかなか実態として難しい。そのため、児童虐待のように時間を区切ることは法律上では見当たらなかった。
⇒(環境省)口頭指導の期間は、正確な数字は持ち合わせていない。私共に自治体から最も相談があるのは「勧告の期限をどうするか」。法23条5項で「3月以内、ただし特別な事情があればその限りでない」とされているが、動物にとって非常に深刻な状況であれば3ヶ月待たずに勧告するという話は聞いたことがある。
・(福島議員)いつまでも口頭・文書指導に留まって次に進まないことは、環境省はどうすれば改善できると考えているか。
⇒(環境省)口頭・文書指導の時は改善計画を提出させる。改善計画にいつまでに改善するか書かせ、それができていなければ勧告するなど具体的な手順をガイドライン等でやっていく。
⇒(Eva 杉本)ガイドラインでは弱いのではないか。
⇒(塩村議員)警察の協力要請に自治体が応じないのは、自分たちが事業者を監督できていないことが露呈することも大きいのではないか。どこを論点にすると双方が歩み寄って結論を出せるか、もう少し研究したほうが良い分野ではないか。
・(神奈川県動物愛護協会 山田様)指導の回数は条文に入れられないのか。
⇒(福島議員)自治体によって事情は様々なので難しいと思う。
(3)飼い主責任(法第7条関連)についての改正案
(公社)日本動物福祉協会・獣医師 町屋様
 業者や一般飼い主などの立場に関わらず、動物を所有・占有しているすべての所有者及び占有者にかかる責務の強化及び明記。
業者や一般飼い主などの立場に関わらず、動物を所有・占有しているすべての所有者及び占有者にかかる責務の強化及び明記。
⇒所有者等の責務を厳しくすることで責任違反の制裁を重くし、動物の所有権に一定の規制をかけやすくする。この規制は、緊急一時保護制度や被虐待動物の没収などに関わるところ。
 第1項条文「動物の健康及び安全~」の後に「快適な環境」を追加。
第1項条文「動物の健康及び安全~」の後に「快適な環境」を追加。
 第2項で、動物の所有者及び占有者の所有する動物に対する感染症予防について述べられているが、以下の遵守項目を追加。
第2項で、動物の所有者及び占有者の所有する動物に対する感染症予防について述べられているが、以下の遵守項目を追加。
動物虐待防止のため策定された国際的原則の「5つの自由」を分かりやすく文章化したもの。
- 適切な食事ときれいな水を適切な量与えること
- 動物種にあった適切な温湿度を保ち、清潔で危険物のない快適な環境を用意すること、雨風や炎天下を避けられる快適な休息場所を用意すること
- 予防的獣医療と迅速な治療等の機会を与えること
- 恐怖・過度の不安・退屈の常態など精神的な苦痛を与えないこと(獣医療等は必要な苦痛とする)
- 所有・占有する動物の本来の生態・習性が十分に発揮できるようにすること
 第4項の終生飼養の例外として「上記項目を一つでも遵守できない場合は、速やかに新しい飼い主等を探すよう努めること」を追加。
第4項の終生飼養の例外として「上記項目を一つでも遵守できない場合は、速やかに新しい飼い主等を探すよう努めること」を追加。
⇒行政職員が立入・視察し、この飼い主は適切な飼養ができないと判断しても、この終生飼養が足枷となり、次の飼い主を探すことを検討しませんかと選択肢を与えられない問題がある。
 第7項に基づき作成された家庭動物等、産業動物、展示動物、実験動物の飼養及び保管に関する基準が全く運用されていない。内容を見直し、現場で運用しやすい内容に改正。
第7項に基づき作成された家庭動物等、産業動物、展示動物、実験動物の飼養及び保管に関する基準が全く運用されていない。内容を見直し、現場で運用しやすい内容に改正。
- 基準が遵守されない場合は、第7条1項違反として行政指導等が入るようにする。程度により「不適切な飼養管理及び動物虐待とみなされる」ことも明記し、第24条、第25条又は第44条と結びつくようにする。
- 前回法改正で制定された「犬猫動物取扱業者飼養管理基準」には、一般の飼い主にも準用できる共通事項もあるので、「家庭動物等の使用及び保管に関する基準」と紐づける。法改正の度に制定された環境省令や通知等を整理していく。
- 産業動物については、農水省作成の「AWに配慮した飼養管理指針」を「産業動物の飼養及び保管に関する基準」と紐づけし、動物愛護管理行政職員や家畜保健衛生所職員等が立入りしやすくするなど、現場で活用しやすい指針及び基準にする。
- すべての基準に、動物福祉に配慮した内容を加え、全体的な見直しを図ることが必要。
(4)意見交換
・(法制局)「適切な食事ときれいな水」など具体的な事項を、動愛法全体に通じる責務として7条にどこまで書けるかは検討の余地がある。法律の建付けとして、ここは守るべきものを様々な場面に適用できるよう、ある意味抽象的に書くような部分なので、今後適切に判断させていただきたい。
・(福島議員)町屋先生のご提案の趣旨を活かすとしたら、例えば政省令を作るのはどうか。犬猫の飼養管理基準も基準を作ることを法律に書き、政省令を検討会で議論したように、検討会で十分練り、コンセンサスをつくって、政省令を作るほうが向いていると思うが、どうか。
⇒(町屋先生)英国の動物福祉法2006は、5つの自由を応用させた5つのニーズという形で項目を条文に入れ、その詳細については、省令やガイドラインのようなものが制定されている。
・(JAVA 和崎様)畜産動物と実験動物は第10条で除外され、その除外が第四節まで繋がっているので、第25条の指導も畜産動物・実験動物は対象外。第7条の基準順守の強化と共に除外規定をなくして、畜産動物と実験動物の飼養に関しても指導できるようにしていただきたい。
・(神奈川県動物愛護協会 山田様)今回も動物愛護法の中には「福祉」又は「アニマルウェルフェア」という言葉は入れていただけないのか。それとも入れる可能性はあるのか。
⇒(牧原議員)別途「動物福祉議連」ができた。動物福祉とは何ぞやということを検討する議員連盟。こちら(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議連)は前回改正で、「福祉というのは基本的に人間のことだ」ということで法制局の段階で終わってしまい、真正面から覆すのは無理だということで、別途福祉の議連ができて検討していただいているというのが私の理解。
⇒(塩村議員)農水のことも入るとここだけでは決めきれず、ここでまとめても党に持ち帰った瞬間に全部はねのけられる。超党派でやっている他の法律も、働きかけが弱い部分ははねのけられている。特に農水関係は、農水関係の議員や、環境関係の議員に部会長含めて働きかけることは非常に重要。ぜひいろんな党に働きかけて、はねのけられないような環境を皆様にも作っておいていただきたい。
⇒(アニマルライツセンター 岡田様)この5年で農林水産省や国会議員の方々も変わってきていて、食料・農業・農村基本法の付帯決議にはアニマルウェルフェアに配慮しましょうという内容も入った。自治体も「今アニマルウェルフェアを推進する方向だからやらなきゃ」とここ2~3年で話すようになった。ぜひ法制局にも「動物福祉」又は「アニマルウェルフェア」という文言の追加をもう一度ご検討いただきたい。私たちももちろん努力する。
⇒(福島議員)農業基本法の付帯決議のような文言を動愛法の条文にも規定するということであれば可能かもしれない。慎重にかつ知恵を絞ってやろうと思う。
第11回 動物愛護法改正PT(2024.06.17)
(1)展示動物(動物園・水族館及び動物カフェ)の飼養に関する現状と課題について
①日本獣医生命科学大学医学部獣医学科特任教授 田中亜紀様
動愛法の対象は哺乳類・鳥類・爬虫類までだが、飼育下の野生動物の福祉について日本は非常に関心が低い。特に野生動物のペット利用について先進国の中でも日本は未整備。象徴的なのが”野生動物を利用したカフェ”。カフェについて本学で実態調査を行ったので紹介する。
①動物カフェについて
- 第1種動物取扱業の「展示・販売」に分類(動物愛護法第10条第1項)。
- 飲食物を販売する施設(飲食店を含む)に野生動物を展示して体験させる新型の業種。
- 台湾や韓国にもあるが、ふれあいは禁止。ふれあいをさせているのは先進国で日本のみ。
- 全国に野生動物を展示するカフェは約200店舗あると考えられているが、未登録の店舗も多いため、実際の数は不明。
②動物カフェの問題
- およそ80種類くらいの野生動物が使われている。
- カフェにいる野生動物の生理習性・生態が理解されていないまま使われている。
- 各種動物の適正な飼養環境、適切な給水給餌が理解されていない。
- 行動や繁殖、ストレス、病気になった時にどう治療すればよいか理解されていない。
- 人に感染する病気を野生動物は媒介する。人獣共通感染症について理解されていない。
 公衆衛生と動物福祉の両方の問題が動物カフェにはある。
公衆衛生と動物福祉の両方の問題が動物カフェにはある。
③野生動物カフェの実態調査
実際に現場に行き、動物たちの飼養環境、飼養管理の評価、動物がどのような状態であるか、異常所見や異常行動があるかを評価した。
約7割のカフェは犬猫で、約3割が野生動物カフェと考えられている。野生動物カフェは全国に約200~300件あり非常に入れ替わりが激しい。本調査では100件程度廻った。
特徴的なのは、外国人の観光客が多い場所に店舗が集中していること。自国では触れられない珍しい動物が、日本ではコーヒーを飲みながら触れるという点で海外の観光客に非常に人気。実際に行って非常に多かったのはフクロウカフェ。その次はハリネズミ、ウサギなど。他にもたくさんの種類の野生動物が使われている。
実態調査の結果
| % | ||
1.収容環境について ・種特異的な行動を発揮できる空間とインフラ ・不適切な動物種や個体を混ぜない 等 |
21.1 47.4 | |
2.ふれあいについて ・制限時間(ストレスやケガの防止) ・動物がいつでもふれあいから避けられる 等 |
17.0 0 ⇒ほとんどが無法地帯 | |
3.栄養と食事について ・適切な食事行動が発揮できる給餌方法 ・適温の新鮮な水、種に見合った給水方法等 等 |
17.5 26.3 | |
4.健康管理について ・異常所見や外傷がない ・ロープ等で保定あるいは自然な行動、正常な行動が制限されていない |
26.3 36.8 ⇒ストレス行動や異常行動が非常に多く見られた | |
5.行動について ・自由に多様な行動を示すことができる ・やりがいのある行動を発揮できる |
33.3 45.6 | |
④野生動物を使用したカフェの問題(まとめ)
- モルモットが多数入っていたケージには死体もあった⇒「死体の放置」は動物虐待罪にあたる。動物虐待の温床にもなっている。
- ふれあいの実態については自由に触れ合える環境なので、動物と人の双方に危険。
- 劣悪な環境から、動物福祉・公衆衛生はゼロ。
- 海外の観光客が非常に多かった。これを見た海外の方々は日本の動物福祉をどう考えるか。日本として恥ずかしいことにならないようにしなければならない。
 野生動物のペット利用に関する規制・基準がないため無法地帯であることは大きな問題。
野生動物のペット利用に関する規制・基準がないため無法地帯であることは大きな問題。
■日本のアニマルカフェの現状と消費者の意識
野生動物:繁殖の歴史も浅く野生の性質を色濃く残している動物。日本は野生動物の消費大国。トカゲ、サル、スナネコ、ナマケモノ等がペットとしてふれあい目的で飼養されている。
①野生動物利用の問題
- 野生から数多く捕まえることによる絶滅の危機。
- 密猟密輸の問題。
- 飼育方法がよく分かっていないために本来の行動が発揮できないという動物福祉の問題。
国が策定している「生物多様性国家戦略」では「野生動物の飼養については、動物の本能、習性および生理・生態に即した適正な飼養の確保が困難なことから限定的であるべき」と明言。⇒今はどんな動物も飼える・触れる状況。そういった消費の在り方は見直す必要がある。
②日本のアニマルカフェの状況
他のアジアの国々と比較して突出してアニマルカフェの数が多く、多様な種が取り扱われている。数は増加傾向。日本のアニマルカフェは2019年時点で137店舗、419種が扱われている。
③野生動物、その他展示利用に関する意識調査
動物を展示する事業者は命の大切さ、動物本来の姿を学ぶ機会や情報を提供すべきだが、カフェの利用が野生動物需要を喚起していたり、野生動物に関する誤った認識を誘発していると思われる。この仮説を検証したく、WWFでは意識調査をおこなった。
日本に住む2000人を対象に、野生動物の中でも特に野生の性質を色濃く残す動物(コツメカワウソ、フェネック、フクロウ、リスザル等)の写真を見せ、これらの動物やアニマルカフェの認識について質問。アニマルカフェ愛好者(半年に1回以上利用)と非利用者に意識の差があった。
●WWFによる意識調査の結果
 愛好者は、野生の性質を色濃く残す動物をペットとして欲しがる傾向にある
愛好者は、野生の性質を色濃く残す動物をペットとして欲しがる傾向にある
「こういった動物を飼いたいか飼いたくないか」を質問。⇒「飼いたい」:アニマルカフェ非利用者は10%、愛好者は半数近く回答。ふれあいについても同様の結果。
 若い世代ほど野生動物のペット飼育意向・接触意向が高い
若い世代ほど野生動物のペット飼育意向・接触意向が高い
アニマルカフェの利用状況を世代別で調べた。30代以下の世代がカフェ愛好者の割合が高く、若い世代でアニマルカフェが一般化しているということが言える。
 愛好者はアニマルカフェで野生動物の正しい知識を得ることができると思っている
愛好者はアニマルカフェで野生動物の正しい知識を得ることができると思っている
「アニマルカフェで動物の生態や習性を学ぶことが出来るか」を質問。⇒非利用者は「学ぶことが出来ない」が76%。愛好者は半数近くが「学ぶことが出来る」と回答。
 愛好者はアニマルカフェの動物福祉が不十分だと知っている
愛好者はアニマルカフェの動物福祉が不十分だと知っている
アニマルカフェは動物福祉が不十分という情報を提示し、その実態を知っていたか質問。
⇒「認識している」の回答が全体で2~3割に留まるが、愛好者は60%以上の方が認知。
⇒愛好者は不適切な飼育がされていることを知りながらも、そこで野生動物の本来の姿が学べると考えていることから、カフェの利用が正しい動物の理解を妨げている。
④動愛法改正提案
- 一般的に飼うことや動物福祉への配慮が難しい動物種を指定する。
- 指定種の飼養は、動物福祉や感染症対策に十分配慮できる事業者のみ扱えるようにする。
⑤最後に
●現在、動物を見ることができるレストランを作るために資金獲得をしているインフルエンサーもいる。一般の方が動物への悪影響、動物利用の在り方についてSNSで多数投稿している。
●海外メディアでも「野生動物のペットやふれあい利用は福祉に配慮できていない、感染症の問題がある」と否定的に捉える発信をしている。海外では、こういったカフェを取り締まる法規制が執行されたり、そもそもペットとして飼える動物を限定するという動きもある。
●動愛法は「人と動物の共生する社会」の実現を目指しているが、正しく理解され、適切に管理されているという目的達成のために何をすべきか、3点お伝えしたい。
- アニマルカフェの海外での増加が今後予想される中、既に特殊な様々な動物を使っている日本が展示業のあるべき姿を示すべき。
- 野生動物は多種多様で、飼育や繁殖に関する知見が不十分なため、種ごとの具体的な飼養管理基準の創設は非常に困難。飼養できる野生動物種を限定する方が実効性がある。
- 多頭飼育崩壊、虐待の問題は野生動物にも起こっている。
■展示動物の飼養に関する現状と課題について
①世界の動物園水族館の流れ
- 「動物を見て楽しむ場」→「地球環境や生物多様性の保全」へパラダイムシフトしている
- 愛護精神の普及に加えて飼育動物に対する「アニマルウェルフェア」が重要視されている
②日本動物園水族館協会(JAZA)の重点的な取り組みについて(WAZAと同様)
 動物福祉の推進
動物福祉の推進
WAZA(世界動物園水族館協会)の2023年動物福祉ゴールを目指し、昨年から会員園館の監査を開始。今後もすべての会員施設に向けた監査を進め、動物福祉の向上に取り組む。
 日本産希少動物の保護増殖(域外保全)の取り組み
日本産希少動物の保護増殖(域外保全)の取り組み
環境省との「生物多様性保全の促進に関する基本協定書」に基づく活動では、ツシマヤマネコの人工授精の成功や、飼育下で産まれたライチョウの雛と親鳥を生息地に帰すことにも成功。
 生物多様性保全の推進
生物多様性保全の推進
主に会員園館で飼育される種の血統登録台帳を作成し、繁殖計画の策定と年間の動物移動を提案。大学とも連携しながら、希少種の精子の保存など配偶子バンクにも取り組んでいる。
 行動変容を目指した教育活動
行動変容を目指した教育活動
JAZAと会員園館が行う各種教育活動は、動物の素晴らしさを知り、動物たちの置かれた現状を知る機会を通じて、自らの行動変容に繋がっていくことを目指している。
③動物園水族館から考える改正すべきポイント
 動物園水族館を第一種動物取扱業から除外
動物園水族館を第一種動物取扱業から除外
現行法で、動物園水族館は第1種動物取扱業の展示業で「業として動物の販売・展示・保管を営利目的で行うもの」とされている。今、動物園水族館の活動は「命の博物館」とも言える公益性の高いもので、ペットショップやアニマルカフェなどの事業とは方向性や社会的位置づけが異なる。私たちのような動物園水族館は動物取扱業から除外していただきたい。
 動物愛護管理法に定義規定を記載(特に動物園・水族館の定義)
動物愛護管理法に定義規定を記載(特に動物園・水族館の定義)
動愛法ではどういう施設を動物園・水族館とするのか定義がないため、当協会が目指すこととかけ離れた内容で営業する施設も自由に動物園・水族館を名乗ることができる。ぜひ当協会のような社会的役割を担う動物園・水族館に対して定義を付けていただきたい。
 科学的・客観的なアニマルウェルフェアやワンヘルスに関する考え方の導入
科学的・客観的なアニマルウェルフェアやワンヘルスに関する考え方の導入
科学的・客観性に基づくアニマルウェルフェアの考えが重要になっている中、動愛法にはこういった言葉が見当たらない。野生動物の利用には、感染症のリスクも考慮する必要があり、ワンヘルスの考えも重要。これらのキーワードを意識したものにしていただきたい。
 野生動物のペット飼育やふれあい利用の制限
野生動物のペット飼育やふれあい利用の制限
野生動物のペット飼育に十分な規制がないため、個人個人が欲しい動物を安易に手に入る。需要が生息地での乱獲を招き、希少種を生み出す懸念がある。アニマルカフェ等で野生動物の生態を無視し終始係留して展示したり、本来人間と触れ合う歴史を持たない彼らへのふれあいは動物福祉の点から問題がある。
 他省との横断的な連携を持った複眼的な戦略
他省との横断的な連携を持った複眼的な戦略
様々な野生動物をペット飼育することで、飼い主からの逸走や、飼いきれず捨てられたりして外来生物化し、在来種への影響や感染症のリスクも発生する。ぜひ横断的な視野での検討を。
動愛法の目的に「人と動物の共生する社会の実現」とある。野生動物の飼育が一般にも広まっている現在では、同法で示す動物は野生動物も網羅した新たな内容にしていくべき。
(2)意見交換
3団体(JAVA,PEACE,ARC)が求める次期動物愛護法の改正事項〈展示動物〉について
PEACE 命の搾取ではなく尊厳を 東様より
 飼養動物のホワイトリスト制:飼育できる動物を指定し、それ以外の動物を飼育不可に。
飼養動物のホワイトリスト制:飼育できる動物を指定し、それ以外の動物を飼育不可に。
ホワイトリスト以外の動物は、どこが飼育できるのかについて。
- 動物園、サファリパーク、水族館:問題がある施設もあり、これらの施設であっても飼育要件を満たさないと飼育できないようにしたい。
- アニマルカフェ、類似の室内展示施設:ケージや拘束飼育等がメインなので、ホワイトリスト以外の動物の新規飼育は不可。業登録も新規の登録は不可としたい。
- 移動動物園:アニマルカフェを外の簡易施設で1日~1か月営業する形なので、2と同様に飼育不可。一定期間経過後は譲渡か動物園など一定規模以上の施設に移行するか選択。
- 個人:新規飼育は不可。現在飼っている方は、特定動物を禁止した際と同じように規制。
 動物展示業に関し、登録の最低水準条項を独立で設ける。
動物展示業に関し、登録の最低水準条項を独立で設ける。
現状の登録は、ペットショップに引きずられており、動物園水族館のように長期間飼育することへの配慮がない。展示業について独立で、最低限必要な条件を条文として設け、その具体的な基準は別途省令をつくることが1番良いのではないか。
 動物園・水族館・展示施設についても禁止事項を定めた条項を設ける。
動物園・水族館・展示施設についても禁止事項を定めた条項を設ける。
- 動物の拘束展示(紐・ハーネス等)を禁止。展示動物の飼養保管基準には既に拘束展示してはいけないと書かれているが、順守義務ではないため全く守られていない。
- ショーや調教芸等の禁止。自然界では行わない動作をさせていたり、ブルフック等で滅多打ちにしている動画もある。これは世界の潮流としてもなくす方向にある。
- 野生動物、畜産動物との触れ合いを禁止。畜産動物は、家畜伝染病予防法の衛生管理基準が守られていないことが多い。日本で起きた集団感染事例の多くは家畜種から。
- 母子を早期に引き離し、写真撮影や触れ合いに使用することを禁止。
- ライドの禁止。動物の背中に乗せるサービス、もしくはショーの一環としてトレーナーが背中に乗ることも禁止。韓国でも動物へのライドは禁止されている。
 移動展示の禁止。
移動展示の禁止。
 基本原則(第2条)に5つの自由のうち「行動の自由」と「恐怖・抑圧からの自由」を追加。
基本原則(第2条)に5つの自由のうち「行動の自由」と「恐怖・抑圧からの自由」を追加。
 動物の飼養者に対し、対人事故を起こした場合の報告を義務化する。
動物の飼養者に対し、対人事故を起こした場合の報告を義務化する。
その他の意見
(日本動物福祉協会 町屋様)①野生動物カフェは、特にコロナ禍で潰れたカフェが非常に多いと聞く。野生動物カフェが廃業した場合の動物の行方はどうなっているのか。
②特に霊長類の飼養をすぐに禁止してほしい。霊長類はニーズが非常に複雑で、人獣共通感染症のリスクも非常に大きい。霊長類はペット、カフェ全てにおいて直ちに禁止してほしい。
③幼齢個体のふれあいを禁止してほしい。幼齢個体が成熟後にトラウマによる異常行動を起こすリスクが報告されている。幼齢個体の確保のため無秩序な繁殖が行われ、多頭飼育崩壊状態のところもある。
⇒(日獣 田中先生)コロナ前とコロナ禍に入ってから3割の店が潰れた。潰れた店の動物たちがどこに行ってしまったのかはほとんど闇。
また、2020年に本学と日本動物福祉協会で動物園の実態を調査し、JAZAに加盟・非加盟含めて全国で200件程度視察。非常に良い動物園と福祉・公衆衛生を全く鑑みていない動物園と差の大きい結果になったので、動物園の定義や飼養環境については対応が必要。
霊長類のふれあいについては私も賛成ではない。霊長類は高等動物であり、身体的なニーズや飼養するのに非常に難しい動物なので、ましてやふれあいに使うことは言語道断。
⇒(WWF 浅川様)イギリスが公表している"アニマルウェルフェアに関する行動計画"の項目には野生動物が入っており、霊長類のペットとしての所有を禁止する法律を制定し、飼養基準をまず霊長類から始めている。日本も優先的にやるべき種を先に決めると良いのではないか。
(環境省)ホワイトリストについては細かく深堀りすると複雑。海外から輸入する野生由来の動物を規制するのか、ブリードする個体も含めるのか、国内で東京にもいるようなカワヘビやトカゲ等を子供が捕まえることも規制するのか。
また、犬猫以外の飼養管理基準は、我々もどうするか検討しているところ。
(JAVA 和崎様)動物園の中でもふれあいをやっているところもあるが、例えば不適切なふれあいをやっている会員の動物園があったとき、JAZAさんはどういった対応をしているのか。
⇒(JAZA 原様)動物園でのふれあいは、JAZAで「動物福祉基準」を決めており、それに反するようなことがあれば注意を重ねて改善を求めている。その制度を導入したばかりなので、これから各動物園のレベルを上げ、様々なステージにある動物園をもっと良くしていきたい。
(神奈川県動物愛護協会 山田様)第1種動物取扱業の中で、動物園や水族館について規定することは可能なのか。
⇒(環境省)動愛法10条の動物取扱業の業種区分の中に「展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)」とある。この定義に動物園水族館は当てはまっているので、さらに動物園水族館の解釈をどこかに追加で書くということは考えられる。
(アニマルライツセンター岡田様)動物園や水族館の定義の話は、アニマルウェルフェア全体の底上げには繋がらないように感じる。JAZAさんに加盟している施設から漏れる展示業は非常に劣悪。さらに娯楽性に注目して新たな展示業が生まれることを繰り返し、どんどん増えて悪化している。これは動物園・水族館の定義がどうかではなく、アニマルウェルフェア上、動物の状態がどうか、その設備が全部満たされているかというところで規制が必要。問題のある新たな展示業が生まれてこないよう明確な規制づくりをしてほしい。
(Eva杉本)野生動物を使った事業は全面的に禁止することが適切ではないか。種ごとに全部掘り下げていくのはキリがない。野生動物を利用したカフェには一つのメリットもなく、様々な角度からみてリスクしかない。
WWFさんから情報提供があった動物レストランは、それなりの企業がやるのかと思いきや、アニマルコレクター的なYouTuberが先頭に立ち、料理系インフルエンサーが協力する形で素人がやろうとしており、本当に恐ろしい。さらにクラウドファンディングの返礼品で"ビントロングのへその緒"を差し上げますと。発想があまりにも酷すぎて言葉を失う。次の法改正を待つ余地がなく、非常に危機感を持っているが、今の法律等でこういった商売を止める術はないのか。これができたら、どんどん他の悪質な事業者が見倣って同じような事業を始める。現状のふれあいカフェのように広がってしまったら止めるのは大変。
⇒(串田議員)動愛法第44条2項で、野生動物を飼養し、身体に衰弱や傷害を与えた場合には刑事罰が発生するのではないか。
⇒(佐藤弁護士)カフェやレストランは食品衛生法など食品に関する法律に抵触するのでは。
別の質問だが、諸外国で台湾や韓国、オランダなどはアニマルカフェや野生動物のペット飼育を禁止しているということだが、他の欧米では規制があるからできないのか。動物福祉の意識が高いからそもそもやろうとしないのか。
⇒(浅川様)イギリスやアメリカでは猫カフェはあるが、野生動物を使うことは常態化していない。イギリスでも動物福祉法など充実しているが、もしかしたら野生動物を扱うカフェが出てきた場合にどこの法律でもカバーされない可能性はあるかもしれない。諸外国では動物をそういう風に扱わないという意識が高い部分はあると思う。
⇒(田中先生)アメリカは野生動物、特に外来種の飼養は非常に規制が厳しい。例えばフェレットはペット飼育不可、動物園など特定の施設でしか飼えない厳しい法律が設けられている。
先ほど串田議員から第44条で対応できないかとあったが、はっきり申し上げてできない。様々な野生動物の虐待案件を本学も扱ってきたが、野生動物の福祉への関心が低いので「虐待」とされない。いくら私たちが獣医学的な知見から虐待だと言っても「前例がない」等の理由で「虐待」と扱われないことが実際にあるので、きちんと法律で禁止するべき。
(福島議員)登録の前に規制することは可能なのか。
⇒(環境省)現行法でも第1種の登録拒否要件は12条で規定。その要件に当てはまれば登録を拒否しないといけない。登録拒否要件は法律本体や省令にもあるが、現行省令上、野生由来の飼養動物については規定がない。しかし、野生由来の動物であってもなくても酷い環境で飼うことは許されていないので、全般的な規制はかかっている。例えばクラウドファンディングでお金が集まらず、明らかに酷い状態で営業を開始するのであれば、登録されないことはあり得るが、現状では業を始める前にその判断をするのが難しい。
(塩村議員)本来飼うべきではない動物がどんどん飼われているのは事実で、それを広めていこうという商売の仕方をペット業界がしている。飼育崩壊が起きたらまた愛護団体さんが頑張らないといけなくなる。大変な問題になる前に考えていかないといけない。
(PEACE 東様)食品衛生法は厨房に動物を置かなければ許可される。食品衛生法では防げないので、きちんと動物福祉の観点からやっていただきたい。
第10回 動物愛護法改正PT(2024.05.27)
(1)強行規定について(前回の続き)
①JAVA,ARC,PEACE 3団体からの要望
 行政は通報を受けたら1週間以内に立入検査に入らなければならない
行政は通報を受けたら1週間以内に立入検査に入らなければならない
- 抜き打ち検査ができる規定を盛り込む。
- 行政措置の対象は第一種動物取扱業者だけでなく、第二種や一般飼養者など動物を所有・占有するすべての者とする。立入りを拒否した場合の罰金(現行法第47条3項)を適用。
- 第44条の虐待の定義を見直したうえで、チェックリストを作成。これに従って確認し、1項目でも該当すれば「違反」認定。⇒虐待かどうか自治体の考え方によって左右されることなく、共通の基準で判断ができる。
 改善を勧告しなければならない
改善を勧告しなければならない
◎特に違反者が動物取扱業者の場合
| 動物の命に関わる重大な違反の場合 | そうでない場合 |
|---|---|
・(改善のための猶予期間として)営業停止を 命じた上で改善を勧告しなければならない ・緊急一時保護も行う ・業者名を公表しなければならない | ・(改善のための猶予期間として)営業停止を命じた上で改善を勧告しなければならない |
 勧告から1か月以内に改善がない場合、命令することができる(⇔現行:3ヶ月以内)
勧告から1か月以内に改善がない場合、命令することができる(⇔現行:3ヶ月以内)
- 1つでも違反が残っていたら改善したとはみなさない。
- この命令に従わなかった場合、現行法第46条第4項のとおり罰金を科す。
- 違反者が動物取扱業者の場合、業者名を公表しなければならない。
 違反者が動物取扱業者で、命令から1か月以内に改善がない場合又は刑事告発の結果有罪判決が下った場合、もしくはその両方の場合、登録の取消しをしなければならない(現行法第19条第4項)
違反者が動物取扱業者で、命令から1か月以内に改善がない場合又は刑事告発の結果有罪判決が下った場合、もしくはその両方の場合、登録の取消しをしなければならない(現行法第19条第4項)
- 業者名を公表しなければならない。
 登録取消し後、5年で再登録できるので、現行法の勧告可能期間2年を5年に改正し、継続して監視や対応を行えるようにする。
登録取消し後、5年で再登録できるので、現行法の勧告可能期間2年を5年に改正し、継続して監視や対応を行えるようにする。
 その他付随して改正が必要な事項
その他付随して改正が必要な事項
- 現行法第10条の実験動物・畜産動物の適用除外を削除する。
- 対象種を脊椎動物に広げる。
- 第二種動取業者を登録制⇒営業停止処分の対象にする。営利性があれば第一種とする。
②(公社)日本動物福祉協会・獣医師 町屋様
1.勧告、命令、立ち入り調査などについて
- 現行法第24条、第24条の4、第25条のように行政の立入りを所有者の立場で分けず、すべての所有者と愛護動物を対象に「都道府県知事は立入りできる(又はしなければならない)」としたほうが、行政職員も運用しやすいのではないか。
- 第25条の内容は多頭飼育崩壊以外の虐待には機能していない。不適切な飼養管理全般に適用できるよう施行規則12条の2と環境省通知の「飼養改善指導が必要な例」の見直し。
2.動物の所有者または占有者の責務等(第7条)の強化
- 動物を所有している人全体にかかるような責任の強化が必要。
- 所有者の責務を厳しくすることで責任違反の制裁を重くすることができ、動物の所有権に一定の規制がかけやすくなる。
3.動物愛護管理担当職員(第37条の3)に新たな項を新設
- 第37条の3に第5項を新設し、知事認定獣医師制度を設置。知事が認定した獣医師で、適正な飼養及び保管に関して専門的な知識を有し、以下の認定用件を満たしている者は立入り・視察など動物愛護管理行政担当職員と同等の権限を持つとする(※農水省の「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」を参考)。これを足掛かりに、愛玩動物看護士もサポートできる形をとれば、運用の障害になっている人手不足の解消の一助になるのでは。
〈認定要件(案)〉
- 獣医師国家資格を有する者
- 国及び都道府県自治体が行う、又は国及び都道府県知事が指定する専門の講習会を終了している者
- 認定を受ける自治体に在住または勤務している者
- 認定を受ける自治体と緊密に連絡が取れる者
- 動物福祉、動物虐待等について専門の知識を有し、その証を持つ者
- 講習会は年に一回必ず受けること
③衆議院法制局
1.検討にあたっての前提
- 「~できる」規定の意義について
行政法の文脈では"してもいいししなくてもいい"ような恣意的な裁量を認める趣旨ではない。具体的には、権限行使が都道府県知事の任意に委ねられていて、要件を満たしていても、特に理由なく権限を行使しないことが認められるという意味ではない。
⇒現行の23条の下でも、当然に都道府県知事としては、法律の目的の達成に必要な場合には法律の権限(勧告)を適切に行使していくことが求められる。
- 「~しなければならない」「~ものとする」規定の意義について
勧告の場面で「しなければならない」と明確な義務の形で用いている立法例は少ない。「ものとする」も権限行使の義務付けであるが若干弱いニュアンスで用いられる。
権限行使についての義務付けの強さ
「できる」最も弱い ⇒「ものとする」中間 ⇒「しなければならない」最も強い
2.考えられる方向性
 「できる」を「しなければならない」・「ものとする」に変える
「できる」を「しなければならない」・「ものとする」に変える
(論点①)自治事務であるが、「しなければならない」とすることができるのか
自治事務であっても「しなければならない」とできないわけではないが、自治事務に関しては地方自治法に「国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮」とあり、なるべく地方自治体の現場の裁量を尊重するような趣旨が求められる。
(論点②)基準不遵守の場合に一律に勧告することが適当か、例外を定める必要はないか
基準を順守していない場合に、常に一律に勧告しなければならないとすることが適当なのか。必ず勧告するにふさわしいような場合を限定すべきではないか検討する必要がある。
 「できる」を維持しつつ、第23条2項で権限行使についての留意等を規定する
「できる」を維持しつつ、第23条2項で権限行使についての留意等を規定する
●動物の愛護及び管理に関する法律 (下線部が改正・追加部分)
(勧告及び命令)
第二十三条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を行うに当たっては、〇〇となるよう留意しなければならない。
(論点)○○の部分をどうするか
「勧告することができる」という規定が23条以外にも24条の2や25条にも登場し、繰り返しの規定になるので、動愛法全体について権限行使の留意等を総則の前後に規定することも考えられる。
3.その他の論点(勧告にかかる改善期限について)
(論点)期限が過度に長期に設定されている事例が実際にあるのか立法事実の確認が必要
改善にどの程度必要かは基本的に事案に応じて様々。長期の準備期間を必要とする場合、かえって原則1月以内とすると表面的な改善措置に終始するといった結果も懸念される。 ※現行法が具体的な期限を法定していないのは、期限は、勧告内容に応じて柔軟に定める必要があり、一律の法定が困難であることを踏まえたものと思料
④動物取扱業者への積極的な勧告等に向けた施策のあり方について(環境省)
1.現状
自治体における不利益処分実施要綱の策定や勧告の件数は以前より増えてはいるものの、勧告、措置命令、登録取り消しなどの措置を実施した実績のある自治体は少ない。
2.今後の施策のあり方
(1)自治体による積極的な勧告について
●勧告の判断基準例や先行事例を環境省作成の指針に反映して自治体に示す
既に「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」という、自治体が動物取扱業者を指導監督する際どうするかを示した冊子がある。これを改訂するなど、以下の例を飼養管理基準違反への対応指針として自治体にきちんと共有していきたい。
- 勧告等を実施する判断基準例
- 勧告等の実施事例
- 立入検査や勧告に係る実務的な課題と対応例
(2)第一種動物取扱業者の違反状態での営業抑制について
 第一種動物取扱業者の更新に係る拒否要件の拡充
第一種動物取扱業者の更新に係る拒否要件の拡充
新規登録時は紙の書類や今後の予定を確認し基準に合致しているかチェックして登録の判断をするが、更新時にはそれまで5年間営業した実績を踏まえて判断できるので、確認可能となる登録拒否要件を拡充し、申請要件も併せて改訂する。
 動物取扱業者間の確認の強化
動物取扱業者間の確認の強化
現在、ペットショップやオークション事業者がブリーダーと取引する際には、ブリーダーに違反や違反のおそれがないか聴取し、あれば取引しないという規定が飼養管理基準にある。具体的な聴取方法や項目を決め、より実効性をもって動物取扱業者間でチェックをしてもらう。
(2)意見交換
(浅田美代子様)前回の法改正から、登録取り消しされた団体や業者は何件あったのか。
⇒(太田記者)登録取消しは2業者あるが、飼養管理基準省令違反の取消ではなく、他の犯罪で逮捕されたから適格要件を満たさず取消しになったもの。飼養管理基準省令に基づいて登録取消しになった業者は一つもない。
(塩村議員)このあたりは難しいところで、人間の方でも、悪質ホストに関してあれだけ問題があっても、ようやく1件営業取消しになった程度。営業の自由があって非常に難しいと言われているが全般的な見直しが必要だと思う。法律はあるので的確に運用してもらう必要がある。
(牧原議員)どのくらいの業者が飼養管理基準を守ってなくて、勧告をしないといけない者がいるのか。改正には立法事実が必要なので確認したい。
⇒(太田記者)調べた限りでは2023年12月時点で、飼養管理基準省令に適合してない業者は103の自治体であった。その103自治体で指導の対象とした事業所は計4997(延べ件数含む)。その結果、勧告まで行ったのが19事業所。命令の対象となったのが4。業務停止や取り消しまでいった事業所はない。(※詳しくは、第7回のレポートをご覧ください)
(アニマルライツセンター 岡田様)環境省の「更新時の拒否要件の拡充」について、更新まで5年かかるので長い。私たちは認定NPOだが最初認定を取ったときの更新は3年だった。最初の期間は短く設定されているので、同じような考え方で、動物取扱業を最初に取ってから1~2年で更新など短いスパンにして問題なければ次の更新を5年後にするという方法もありかと思う。
⇒(環境省)我々も議論していて、当初登録するときは動物がいない状態なので、運用してみないと判断できないところもある。登録にあたって書類で確認した後に、どのタイミングでそのチェックに行くのかは重要になってくると思う。検討します。
(神奈川県動物愛護協会 山田様)立入検査の抜き打ちについて、廃棄物処理法の平成2年の通達で「原則としてあらかじめ連絡することなく立ち入ること」とあるが、例えば現状で劣悪な時は「連絡することなく立ち入る」旨の通達は出せるのか。
⇒(環境省)環境省作成済みの動取業の解釈と運用指針の中に、抜き打ち検査が有効な場合もあるし、法律上何ら否定されていないということは記載している。自治体向けの研修でも抜き打ち検査は有効な場合もあるのでそれも踏まえて実施するよう伝えている。
(町屋先生)通報から立入りまでの期間も法律で定められていないため、非常に長い期間立入りを拒否している第一種動物取扱業者が実際にいる。やはり通報を受けてから立入りに入るまでの期間もある程度定める必要がある。
⇒(環境省)行政として勧告などに踏み込めないという状況が実際あって、団体と行政間でずれがあると思う。期間を定めることについては、我々も必要なステップを踏む必要はあると思うが、何回も指導する方が逆に労力がかかるのではと正直思う。人が足りないのであれば期間を区切るほうが良い。我々も何故に口頭指導を繰り返して、改善させることができない状態なのか、その方が大変じゃないかということは話していきたい。
(福島議員)立入検査や勧告などに期限を区切っている他の立法例はありますか。
⇒(法制局)ぱっと思いつかないが、動物の生命に重大な危機が及ぶような場合に類似するようなものはある。例えば児童虐待は法律ではなかったと思うが、運用で期限が定められていると思うので「生命の危機」という観点では十分参考になるのではないか。(Evaコメント:児童相談所が虐待通告等を受けた場合には”速やかに”子どもの安全確認を行うよう努めなければならない[児童虐待防止法第8条]。安全確認が必要と判断される事例については、通告受理後、迅速な対応を確保する観点から、48時間以内とすることが望ましいとされている[参照]厚労省ホームページ「子ども虐待対応の手引き」第4章より。)
(牧原議員)ここは前回の法改正でも問題になった。自治体に聞くと「なかなか受け入れられない」と。上が決めても実際にやる人たちに伝わらないと実効性がなくなってしまうので、環境省には自治体の皆さんがなぜこれを実行できないのか、理由や実態をぜひ探ってもらいたい。警察は慣れているはずだから立入りに行けるが、行政の職員は怖い人の所に行って注意するということ自体に心理的な負担を受ける可能性がある。実効性をどう高めていくかを含めて、地方の意見をもらいたい。
(山田様)食品衛生では、指導員や監視員の制度がある。環境衛生指導員、監視員もあって獣医師も入っている。例えば動物愛護法の中で動物愛護指導員・監視員という形で人員を増やすことは可能か。環境衛生監視員は警察の出向もあるようなので、前例として運用できないか。
(Eva 松井)劣悪飼養が続いていた長野県松本市の裁判を傍聴した時、オーナーと行政の職員との関係性は良かったという証言を聞いた。「大変ですね。お体大事にしてくださいね」と言われていたそうで、行政がその施設を適切に指導していたとは到底思えない。環境も山の中で劣悪で、もし女性職員などが行くとなるとやはり怖いんじゃないか。オーナーの性格が荒々しいと余計に行政職員も怖くて違反を指摘しづらいと思うので、そういう関係になってしまった部分もあるのではないか。怖いから、面倒だから指導しようとしない傾向もあるだろうから、やはり警察や、町屋先生のお話しにもあった知事認定獣医師を同席させて、認定獣医師が虐待を認定できるようにし、虐待の判断を行政だけに託さないようにするといいのでは。ただ、虐待現場に警察と入って「これは虐待じゃない」と判断してしまう獣医師もいて押収できなかった事案もあったので、虐待に特化した教育を受けた認定獣医師に現場に一緒に入っていただき、違反かどうかを明確に判断していただきたい。
(細川弁護士)登録取消しを「しなければならない」とする例としては建設業法がある。また、動愛法と同じ登録制で「しなければならない」という規定があって中身が厳しめな例には貸金業法がある。動愛法と共通することが多いのでこれは参考になるのではないか。
(PEACE 東様)食品の方で、業者が保健所を気にするのは、やはり食中毒を出せば営業停止になるからだと思う。少しでも表記を違反すると全商品回収になり、改善している間は売れない。動物に関しては営業停止して改善させることもできていないので、やってほしい。運用面で最近困っているのは、通報しても自治体が個人情報だからと言ってその結果を教えてくれなくなっている。以前は改善したかどうか教えてもらえていた。どうなったか分からないままうやむやになって終わることが増えているので、通報者への説明もやっていただきたい。
(岡田様)法律は抑止力が重要なので、立入りを拒否されたら既に法律にある罰金を科すことが1件でも起きれば事業者も拒否することはなくなるはず。これがないから行政が何回も訪ねるということがずっと続いて、結局人手不足という風になっている。きちんと今ある法律をつかって人員を回す方法もあるので、それが運用しやすくなる方法を考えたい。
事業者が怖くて指導できないというケースは、ある県と話したときに実際に彼らも言っていた。私たちも視察に行くと怖い人もいるのでその気持ちはよく分かる。でも勧告はその場で知らせなくても、郵送でいいのでは。行政と獣医師と警察で見に行って、違反点を洗い出して郵送。そうすれば少なくとも危険は及ばないので、安全の確保もある程度できるのではないか。
(町屋先生)行政職員の立入りの心理的負担が非常に大きいことの一つに国賠を恐れているという話もある。だったら法律で細かく定めて法律のとおりやったという言い訳が立つのでは。
(塩村議員)ホストの件も、警察も国賠を覚悟のうえで取消したと話していた。どれだけの犠牲が出ても国賠を恐れてなかなか動けないところが1点と、民法や憲法があって踏みとどまっていることもあるが、そこで踏みとどまっていては改善されるものが改善されない。動物愛護法はそこを乗り越える第1歩にしていかないといけない。動物は変わったのに人間のほうは変えなくていいの?という風にできたらいい。
第9回 動物愛護法改正PT(2024.04.22)
(1)「長野県松本市における動物取扱業者への対応に係る検証報告書について
(通知)」<環境省>
「長野県松本市における動物取扱業者への対応に係る検証報告書について(通知)」(令和4年3月15日付)とは、長野県松本市で極めて悪質な第一種動物取扱業者の虐待事案を受け、長野県が適切に指導できなかった事を反省し、検証報告書にまとめたもの(「動物取扱業者への対応に係る報告書」長野県 令和4年3月11日付」)を、環境省が全自治体に『動物取扱業者への指導の参考にしてほしい』という趣旨で通知を出したものである。
■検証結果のまとめ(長野県)
【背景】
- 動愛法に基づく措置(勧告・命令・登録取り消し等)の執行が長野県では前例がなく、実質的に非常に困難なものと思い込んでいた。
- 動愛法改正の度に動物取扱業者への規制が強化され、その趣旨などに対応した実施事務を行う自治体としての主体的な考えや行動ができなかった。
- 動物取扱業者の指導を担う保健所の業務が増加しており、動物取扱業への監視指導業務の優先度が低くなっていた。
【実態】
- 長年にわたる不十分な指導、具体的には、繰り返し同じ指導を重ねることに留まり、実際の動物の環境改善に至らなかった。
【問題点】
- 立入検査体制の不備
・「指導困難事例」として積極的に対応することが出来なかった。
・事前通告してからの立入検査を繰り返していたため事実を的確に把握できなかった。 - 不適切な動物取扱事業者に対する行政措置の手順等の未整備
・悪質な動取業者にどのように指導していくのか、手順なども整備されていなかった為、結果的に指導を繰り返してしまい、さらなる行政措置を検討できなかった。 - 情報共有等の不足
・保健所内や本庁との間で情報共有が行われなかった。 - 警察等の関係機関との連携不足
・保健所のみで対応しており、虐待事案の捜査を担う警察との連携が不足していた。
【改善策等】
- 立入検査体制の充実・整備等
・事前通告や抜き打ちによる立入検査を組み合わせて実施する。
・本庁等に広域的に動物取扱業者等の立入検査を行う職員の配置⇒担当保健所職員と共同で立入検査 。
・担当職員の研修会の開催⇒監視指導の標準化や職員のスキルアップをしていく。 - 勧告、措置命令等に係る適正な行政措置の手順等の整備
・勧告、命令等の行政措置の手順を定めた文書(不利益処分実施要領)の整備 ⇒「指導困難事例」等に対しても、一定の具体的対応が可能。(※下記ポイント解説参照) - 「指導困難事例」等について積極的な情報共有と連携した対応
・本庁と保健所との連携 - 警察等の関係機関との連携強化
勧告、措置命令等に係る適正な行政措置の手順等の整備のポイント!
改善注意票などにより2回の指導を行ったにも関わらず改善が確認できない場合は、顛末書及び改善計画書を保健所長宛に提出する。その後は不利益処分等のフローチャートに則り進んでいく。何度も指導を繰り返す事を無くした。
長野県 動物の愛護及び管理に関する不利益処分等実施要領について(通知)(令和4年1月26日)
■不適正な動物取扱業者への行政処分等に向けた環境省の主な取組等
- 飼養管理基準違反に対する対応を整理・周知
「動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」において、飼養管理基準違反に対する対応のフローチャートや勧告・措置命令等を発動する違反例等を整理し、都道府県等に周知した(令和3年5月)。 - 長野県検証報告書の周知
長野県がとりまとめた「動物取扱業者への対応に係る報告書」(令和4年3月11日)を受けて、概要や不利益処分等実施要領の作成の有効性について、技術的助言として全国の都道府県等に通知した(令和4年3月15日)。
(※上段で説明した「長野県松本市における動物取扱業者への対応に係る検証報告書について(通知)」のこと。) - 自治体向けの研修
自治体向けの動物愛護管理研修において、長野県等から講師を招き、不適正な動物取扱業への対応をテーマとしたグループワークを開催した(令和4,5年度)。 - 勧告・措置命令等の状況を把握
毎年、自治体による勧告、措置命令等の状況を把握している。
(※下記はその表)
勧告・措置命令等の状況
| 第一種動物取扱業者 | R2年度(2020年度) | R3年度(2021年度) | R4年度(2022年度) |
|---|---|---|---|
| 事業所数※4/1時点 | 46,929 | 48,395 | 48,557 |
| 立入検査(施設数) | 15,403 | 16,288 | 21,493 |
| 立入検査(件) | 18,778 | 20,701 | 25,919 |
| 勧告(件) | 6 | 11 | 19 |
| 措置命令(件) | 2 | 0 | 1 |
| 登録取消命令(件) | 3 | 2 | 1 |
| 第二種動物取扱業者 | R2年度(2020年度) | R3年度(2021年度) | R4年度(2022年度) |
|---|---|---|---|
| 事業所数※4/1時点 | 1,256 | 1,472 | 1,604 |
| 立入検査(施設数) | 390 | 387 | 539 |
| 立入検査(件) | 556 | 518 | 748 |
| 勧告(件) | 0 | 0 | 0 |
| 措置命令(件) | 0 | 0 | 0 |
※なお、飼養管理基準違反に対して勧告を行わなかった事例として、文書・口頭指導により改善がみられた又は改善見込みがあった、廃業したなどの事例がある。
(2)飼養管理基準省令の運用状況 <朝日新聞 太田匡彦記者>
飼養管理基準省令の運用がどの程度できているのか、という観点から、今回の法改正の1つのテーマでもある「改善勧告」や「改善命令」を強行規定にすべきではないか、という点についての指摘をさせて頂きたい。
■飼養管理基準省令の運用状況
2021年~23年のいづれも12月に全国129の動物愛護行政を担う自治体に「飼養管理基準省令はどのように運用されているか」という調査を実施。(回答率100%)
第一種動物取扱業者への監視・指導を行う自治体はその内107。
【立入検査の実施状況】
そもそも飼養管理基準省令の順守状況については、立入検査をしなければ実態が掴めない為、2023年12月時点でどの程度立入検査が終わっているか確認をした。
- 立入検査を終えた:34自治体
- 23年度中に終了予定:20自治体
- 24年度中に終了予定:26自治体
- 終了のめどが立っていない:27自治体
立入検査がなかなか進まない理由
- 1件あたりの検査時間が1時間程度に増大した。
- 人員不足で立入検査の時間が確保できない。
【飼養管理基準省令の効果】
- 実効性の高さを評価する声が多く集まった。
- 安易な動物取扱業の登録申請が減った。
- 省令の施行を理由に廃業した業者があったとする自治体は31にのぼった。
【飼養管理基準省令の問題点】
- 勧告や命令は業者にとって重い処分なので慎重な判断をせざるを得ない。
- 何とか改善してくれるよう繰り返し指導するしかない。
- 1日3時間以上運動場に出しているかについては確認のしようがない。
- 繁殖引退動物が飼養管理頭数に入らいないことが抜け道となっている。
- 飼育ケージの最低面積などについての規制が既存業者にも施行された直後から純血種が放浪していることが相次いだ。 e.t.c...
【結論】
飼養管理基準省令は犬猫の健康や安全を守るために定められたものであり、明らかになった課題に対しては、各自治体・環境省・業界団体で、法令順守をいかに徹底できるか、より一層の努力を払い知恵を絞るべき。
- 環境省は、より実効性の高い規制にするため、省令の随時見直し改正を。
- 「レッドカード基準」として機能させるためには、動愛法第23条(勧告及び命令)及び第24条(報告及び検査)を改正して「強行規定」に。
(3)意見交換
(Eva杉本)長野県だけではなく、大阪府の繁殖場でも、何度も何度も行政指導が繰り返されたが結局改善されなかった。たとえ行政が入って様々なチェックをしても、外観だけを見ている。動物そのものを触って状態を見ていない。それで指導を繰り返すだけで改善に至らないという問題は、全国的にどこでも起こっていて、マンパワー不足であるならば余計にきちんとタイムリミットを設けて勧告、命令までステップアップしていっていただきたいというのが私たちの強い要望。
(日本動物福祉協会 町屋様)実例として、勧告に行く以前の現在進行形で行政の立入りを拒否している展示施設についてご紹介させていただきたい。当該施設は以前から国内外の旅行者を中心に苦情が多く、当協会も一昨年、季節を変えて3回ほど現地視察をした。
その結果を踏まえて、昨年4月に260ページに及ぶ報告書と共に管轄の自治体に視察・指導の要望書を提出し、行政自体はすぐに立入りの準備をしてくださったが、当該施設のほうから立入りを頑なに拒否され続けおり、今年の3月に管轄の自治体に状況を確認した時点でもまだ立入りすらできていない状況にありました。
こういった問題は、やはり穏便に何とか進めたいという自治体側の方針というのもあると思うが、虐待や不適切な飼養管理疑いの通報があったときに立入りできるというような法的根拠がないために、なかなか強行的には入れないというところも問題としてあると思う。
そもそも、現行法では行政の立入り自体が、1種は24条、2種は24条の4、一般は25条第5項と分かれているので非常に運用しにくいという側面がある。業者であろうが一般であろうが動物の所有者ということに変わらない。すべての所有者とすべての愛護動物を含めて一律に虐待または不適切な飼養管理が疑われるような通報を受けた場合は、都道府県知事は立入りできると、そういう風に一つにまとめたほうが行政側も運用しやすいと考える。
また、その第25条の内容は公衆衛生が主となっておりますので、多頭飼育問題以外の問題には実は機能しないという実情がある。なので施行規則12条の2(虐待を受けるおそれがある事態)の記述に、不適切な飼養管理の具体例を明記していく必要があると思います。この不適切な飼養管理というのは、すべての動物に関わる内容になると考えている。
(JAVA 和崎様)行政の手続きの処置のことについては「できる」から「しなければならない」という義務規定にすることに賛成。また、1回目の指導から改善確認まで時間が経ってしまうと動物も衰弱し、最悪死亡してしまいかねないので、できれば1か月以内。通報を受けて最初の立入りするまでに時間がかかってしまうといけないので、通報を受けてから1週間以内の立入も必要。また、複数問題点があった場合に、1点改善したからそれで良しではなく、問題点がすべて改善するまでの期限を1か月以内にして頂きたい。あとは職員の方が適正に指導できるように、職員の方への教育というところも今度の改正に入れていただきたいのと、やはり指導は決して犬猫に限らず、劣悪な飼育、販売展示されている動物、愛護動物全般を対象にしていただきたい。
(Peace 東様)25条の見直しについて一つ明確にしておきたいのですが、実は25条の適用除外というのがある。動物取扱業の適用除外になっている実験動物・畜産動物が25条まで適用されている(=実験動物・畜産動物は25条まで適用除外になっている)
これは非常に問題だと思っていて、いま私たち3団体で取り組んでいる茨城県の畜産センターの劣悪飼育や牛への暴力っていうのを刑事告発しましたが、それ以外にも改善していただきたいことはあるが、この件も茨城県の動物愛護行政は一切関わらないと言っている。それは動愛法に明確に25条が適用除外されているし、動く根拠がないと言われています。実験施設でもあるので、劣悪飼育が起きることはありますし、そもそも動物取扱業の適用除外をなくしてほしいというのが大きな要望ではあるが、それが通らなかった場合にまでこの適用除外が引き継がれるっていうことだと非常に問題。以前、東京大学の外で飼っているヤギがすごく痩せていたっていうこととかも、東京都のセンターは何も動きませんってことだったので、それでは動物の福祉は全く担保できない。
あと、環境省からご説明いただいて、法律にないので当たり前だと思うが、どのくらいの業者が指導を受け、特に文書指導に至っているものはどのくらいなのか。おそらくこの立入検査と勧告の間にものすごく大きな数の差があるが、この間に不適切な指導報告書を受けられている業者がたくさんいると思う。実態把握をしていただきたい。
(塩村議員)環境省に伺いたいが、例えば「~できる」を「しなければならない」という風に法改正した時に、なにか問題があるのか教えていただきたい。
(環境省)先ほど1か月以内という話がありましたが、措置命令や登録取り消しは原則として行政手続法に基づいてやらなくてはいけないということがあるので、その手続きを経ていくと一定程度時間がかかっていくのは動愛法とは別にやむを得ない部分はあると思っている。なので強行規定を導入する場合にも行政手続法と齟齬がないようにしなくてはいけない。
もう一つの「~しなければいけない」とすることですが、地方自治の関係でこれが「都道府県知事がしなければいけない」ということが法的に規定できるのかどうかというところは、動愛法に特化した話ではないが、こういった事例があるのかを含めて確認はしていないがなかなか難しいところあるのではないかという感覚はある。
(牧原議員)前回の法改正でも議論になった。前回も地方に対しての義務化、あるいは1か月以内とするのは、最後、地方に意見を聞いてみたところ却下された話であったと理解している。
地方自治体に対する法律上の義務づけないし努力義務というのは、必ず知事会とか議長会とか市町村会に確認を取っている。そうしないと、以前義務化を一部したことがあったときに地方からも猛烈な反発があった。結局我々が予算づけをするわけではないので、都道府県や地方自治体によっては職員の規模やその都度の状況が違うので、一律な国からの義務付けというのは一般的にそれは難しいよね、というのが我々の相場観。一方で聞いてみるというのはできると思う。何らか道を探る方法はあると思う。
(アニマルライツセンター 岡田様)行政が動かないことにより非常に多くの動物たちの苦しみが発生したというところで、今回の改正ではやはりここを何とか改善することで、動物虐待に具体的に踏み込んでいきたいと思っている。そのときに義務規定が難しい、あるいはお伺いを立てなくてはならないというのであれば、そのほかに行政がきちんと動く仕組みを考えなくてはならない。また、指導とその次の勧告へ行く数の落差があまりにも大きい。この指導をまずやめていただきたい、そのまま直接違反していたら当然勧告をしていただきたい。それが動物虐待の罪に第44条にあたっているのであれば、勧告もしながら一緒に告発もしていただきたい。この辺りをスムーズにするというところでいうと、考えられるのは義務規定なんですが、それ以外に何か考えられるものが環境省であるんでしょうか?
(串田議員)一言足すと、立入検査は原則抜き打ちでなければならないとかいうようなことは環境省として構わないか?というのは、あらゆる面で勧告とか少ないのは、抜き打ちでなければその場しのぎで何らかの形で体裁を作ることができるのでこんなに少ないんじゃないか。立入検査を抜き打ちでなければならないというようなことを入れるのは地方自治体として別に抵抗はないと思うのですがどうでしょうか。
(環境省)抜き打ちのメリットは当然認識している。我々も研修で抜き打ちのほうが効果があるとしているが、一方で自治体も人と場所の問題などがあって、不在ですというのを逆に使われてしまうとかそういったデメリットもあると思う。当然、抜き打ちが効果的であるのは認識していますし、そういったことをやらないといけないということは我々も伝えていかないといけない。
長野県はこの事案を通じてかなり改善した。それは職員の能力向上も含めてあったんだろうと認識している。通知も令和4年3月に出しているが、色々な通知を出しているので、少ししつこいぐらいに出していくなど、こういった長野県の事例も参考にして促していくことも最低限必要。それで全然義務的ではないだろうと言われるとごもっともだと思うが。
(アニマルライツセンター 岡田様)まさに全く十分じゃないと思っていて、100以上ある自治体の中の一つが改善してもだめですべてが改善しないといけない。そのときに行政の方々がきちんと改善ができるようにするのが義務規定であって、それがないとやりにくいんじゃないかと思う。今回の改正の特に愛玩動物であれば、ものすごく大きな肝がこの行政による勧告・立入の義務化だと思うので、これをなんとか実現したい。これはどこかにお伺い立てずにするのは難しいのか。
(牧原議員)前回、環境省に相談窓口を作って、必ずまず環境省に相談がいって、環境省から地方に行くと地方も無視できなくなるのではないかという議論をしたが、今度環境省の動物愛護室が十数人なので、全国からその通報を受けるのはとても無理だという話になったりした。義務規定にするとこういう場合は例外だというのを作っていかないといけない。
あとは警察との連携が重要だと前回もあったが、これはかなり進んだと思う。昔は警察は全く動かなかったのが、だいぶ前回の法改正を通じて動いたので、警察のほうに相談をしていただくというのも一つだが、法律に書き込むのは難しい。
(福島議員)獣医師が虐待を発見した場合は通報しなければならないってなっている。だからこういう風に「しなければならない」が有効になる場合もあるけれど、行政だと「しなければならない」となるとやらないことがあとで国家賠償請求訴訟じゃないけれど全部問題になるのでどうなのかなと。逮捕勾留も逮捕勾留できる要件はあるけれど「しなければならない」となっていないから、でもなにか前回とは違う一歩前進を勝ち取りたいですよね。ただ、行政も本当に人が足りないのに「しなければならない」とか、あるいは「1か月以内に」という日程はたしかに厳しいか。今ここで結論が出せないですが、「しなければならない」とすると例外規定を設けるとか...
(太田記者)せめて勧告のところだけでも強行規定にできないか。命令や登録取消は処分で、処分は重いが、勧告は処分ではない。せめてここだけでも強行規定にできないかというのは思いとしてある。ここをやらないと結局無理なんです。
もう一点、もし可能性があるとしたら、飼養管理基準省令を登録要件にできないか。いま登録要件になっていないので、登録した後に行政がこの省令が守られているかを確認しに行って、それで守られていなければ勧告命令という話になる。この飼養管理基準省令自体守っている施設ではないと登録できないという建付けにはできないか。従業員の確保も含めて。登録時には何頭飼養するかも一緒に登録する。だからそれに見合った雇用をしている状態かも含めて。
(環境省)登録の要件にできないのかという指摘について、現在も動愛法第12条に基づいて一定の場合に登録を拒否しなければならないという要件が定まっている。その要件の一つとして、「動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき」という基準があり、それに関連して飼養管理基準の第2条第1号(飼養施設のケージサイズ等)の飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合するものであること、という基準がもともと入っているので、たとえば基準違反のケージしか用意してなくて登録を認めてくださいと言ってもダメですというルールにはなっている。更新の時も適用される。
(太田記者)ハード面は登録要件になっているという話ですが、設備の図面を出すだけ。繁殖回数についてはやりようがないが、できる部分については立入りをしたうえで見ていかないと、移動販売がなぜ省令を適用できないかというと、登録の図面だけ見ればかなっているように見えるが行ってみたらそうなっていないという状態で、そのうち逃げていくというのが移動販売の問題。図面だけではなくて実際に立入りをしてというところまで含めてやらないと実効性という意味では意味がない。
(Peace 東様)まさに前回の改正で私たちが立入検査を登録の前に義務化する、立入りしないと登録できないという風に要望していたが、なぜか義務化できない、ということで前回通らなかったが、私たちはそれが必須だと思う。
移動動物園なんかは見ないで書面だけで登録番号を取っている。「それは現地に当日行って合ってなかったらやめさせるんですよね?」と聞くと「もちろんやめさせますよ」と自治体の人は言うけれど、もう登録番号取っているので、不適切な状況であってもそれでされてしまっている。私たちも見に行ってあとから指導してもらうってときには移動展示業者はもうそこにいない。ですので、やはり登録前の事前立入りは必須だというのは間違いない。
あと私たち3団体の要望として今回追加しているのは、職務怠慢な自治体があったとき、期限内の勧告を怠った場合とかに環境省から自治体への指導ができるようにするていうこと。これは地方自治法第245条の4~8号に規定があるそうで、建築基準法などではそういう規定があるので、こういう形で環境省が関われば一定の水準に保つということができるようになるのではないかと思う。製薬会社がまずいことをしたときに自治体の方と厚労省の方が一緒に立入りに行ったりしているので、あんまりひどい場合にはそういうこともできるような形にしていったらいいのではないか。
(環境省)第一種動物取扱業者の登録数は2万以上ある。5年に1回更新とすると全国で均すと4000。それを考えると、現状の自治体のマンパワーで毎年来るものを1個1個確認するのはなかなか難しいだろうとは思う。法改正するからには人を増やせる状態にしていかないと結局図面で見るしかないんです、となってしまうところはあると思う。
(新潟市動物愛護センター 登坂様)
レッドカード基準について一つ。長く食品衛生のほうで仕事をしてきて営業停止命令にずっとかかわってきた。その基準を読んだときにレッドカードじゃなくてイエローカードを何回か出して最後レッドカードにたどり着くので非常にやりにくいなと思っていたが、食品の世界でいうと、食品衛生法という法律が非常にやりやすくなっている。行政処分って懲罰だと思ってらっしゃる方が大勢だと思うがそうではなくて、食中毒の営業停止の時は直させるために、その原因を究明してそれを改善するためにこれだけの期間必要ですから休んでくださいね、というのが営業停止。それを動物の世界にもってきたときにどういうやり方があるのかは私もいい方法は思いつかないが、なにか間違ったことをやっていてそれに緊急性があって弁明の機会の付与をすることなくそのまますぐ営業停止という形にできれば、行政の職員としてはやりやすいなと思っている。具体的に動物の世界ではそうかという案はないが参考までにお話しさせていただいた。
食中毒の判定をする時には、保健所の専門の職員を集めて食中毒判定会議というのをやるが、長野県の報告書にも専門家に情報共有してというのがあったが、それに近い形じゃないかなと思っていて、そういうやり方もひとつあるのではないか。
(神奈川県動物愛護協会 山田様)
ここのところ相談があった事例で、販売されている動物の腸内寄生虫とかケネルコフとか病気の動物をそのまま売られた、というご相談をいただいている。立入検査の時に、便であったりそういう検査ができるもの、実際にこういったものが出ましたよというのが出せるものをちゃんと採取してくるとか、なにか疑いがあればそれを行うというようなことだけでもいれていただけないか。
(Eva松井)
そもそも行政が虐待が起こっていると認めないケースが多い。大阪府寝屋川市の施設でも、警察の家宅捜索後、死亡した犬がいたにもかかわらず府のほうは中に入っても虐待の疑いのある犬は見当たらなかったというような判断をしている。それは長野の事例でもそうだった。何年にもわたって中を見ていたにも関わらずこれは虐待ではなかったと判断する。長崎であった事件でもそこに動物の死体があったのにもかかわらず自然死だろうと行政は度々いう。
行政が何を根拠に言っているのか通報した側としては知りたい。何に当てはまっていないからというのを示してほしい。虐待の定義を細かく定めて、これに当てはまってないから虐待じゃない、これに当てはまるから不適正飼養が起きているということを明確にしてもらわないと、行政も憶測で虐待じゃないという。通報した側としても改善してほしいから言っているのに思ったような答えが得られないとなると、そこで問題が止まってしまう。
(串田議員)虐待と認めたら次に進まなければいけないから虐待ではないと言い張るんでしょうけど、環境省としては虐待ガイドラインを作っていてそれが足りないと言われたのと同じではないかと思う。
(福島議員)「勧告することができる」という25条の末尾を「勧告しなければならない」とするのは一つありなのかもしれない。だってこれ飼養管理基準だから割と明確にいえる場合がある。ケージがってない場合にはできるから、これは勧告するっていうのは一つの方法ですね。
(串田議員)ただその前提として、「遵守していないと認めるとき」っていうのを認めない。
(福島議員)ただ飼養管理基準は認める認めないというのはあるけれど、認めざるを得ないことも多いのでは。
(串田議員)認めないときにその事由を公表するとかっていうことですよね。ここの部分で認めないっていうのは想像できますよね。認めちゃうと次いかなきゃいけないから。
(4)動物の一時的かつ緊急的な保護 自治体からの意見(環境省)
■自治体において一時的かつ緊急的な保護が必要と感じられた事例
- 動物が衰弱している等にも関わらず飼い主や所有者が不在であるため所有権に関する意思確認が困難な事例
例)飼い主の一時入院・死亡・逮捕など
- 虐待により動物が衰弱等している等にも関わらず飼い主が所有権を放棄しない事例
例)多頭飼育崩壊、飼主による虐待など
1.のどうしようもなく飼い主がいない、という分かりやすいパターンの時は比較的判断がしやすいが、2.は、まさに先ほど虐待を自治体が認める認めないの話があったが、数値で基準を設けるのが難しい中、判断が難しく運用に課題が生じるだろうという懸念点がある。
■自治体から寄せられた懸念
- 収容能力や飼養管理要員が足りず対応できない懸念
犬猫以外の動物は収容できないことや衰弱した動物への専門的な獣医療措置に対応できる人材や治療費等予算不足 - 動物の病気や死亡時における管理・賠償責任を自治体が負う懸念
- 基本的人権を侵害(動物の剥奪や治療・土地建物への立入)する懸念
そのほか「適用基準や期限の明確化も必要」「飼い主に戻したら虐待される懸念も踏まえれば一時保護ではなく永久保護ではないか」「財産の差し押さえの手続きに一定の時間を要するとそれで実効性があるのか。」との指摘も。 - モラルハザードの懸念
「飼い主責任放棄の助長に繋がるのではないか。」
「有料引取りとの違いを付けられない。」との指摘も。
全体として緊急一時保護自体に反対するというよりは、あった方がいいというのと、少し厳しいのではないか、と考えている自治体、半々くらいだった。
第8回 動物愛護法改正PT(2024.04.08)
(1)8週齢規制への対応状況、飼養管理基準省令の遵守状況、繁殖業の許可制、移動販売禁止について関係者ヒアリング:
①ペットパーク流通協会 上原会長、大友事務局長
環境省の調査結果が出て、我々も指導・管理ができなかったことを皆様に深くお詫び申し上げます。
1.8週齢規制をめぐる出生日偽装について
■ここまで出生日偽装が根深いものになった原因
- 出生日を担保する仕組みがない中での出荷日齢の規制強化
- 一般消費者の需要が高いために生じる、小さい子ほど高値になる市場の状況
- 問題のあるブリーダーに注意をしても、規則や罰則の無い当協会以外の別オークションへ流れる不適切な競争環境
- 犬において、母親の移行抗体が残っているうちに出品することで、感染力、致死率の高い感染症による死亡を防げるという根強い商習慣
顧客であるブリーダーへの指導・教育による矯正には限界があると感じていた。今回、行政のメスが入ってくれたことは業界としても良い機会だと考えており、協力してブリーダーへの指導、教育、取り締まりを行うことで業界の体質改善を図っていけるのではないか。
■対応策
- 獣医師による出生証明、出品時の門歯・体重の確認、問題のあるブリーダーの出品停止と指導
- 出生時の情報を記録・開示できるシステム(※)を構築し、出荷時に提示を義務づける(流通協会の全てのオークション会場に導入する予定で現在作成中。)
※システム案(流通協会で開発中のシステムの一例)
- 親犬生体の情報を登録
- その親のかけ合わせから新たに出産した生体の情報の登録を、出生日から2日以内に写真で登録
- 15日単位で生体の写真と体重を記録(※成長記録は各日の前後3日以内など制限予定)
2.一部業者による移動販売について
実店舗を持たない移動式販売では、飼い主側が販売後のアフターフォローを受けがたい。言い方は悪いが”売り逃げ”のようなことの発生リスクを考えると廃止するのが妥当と考える。
■対応策
移動式販売を実施しているのは業界内で2社。それぞれに話を伺ったところ、移動式販売の終了は既に考えており、自家繁殖・自家販売へと業態を切り替えようと準備を進めているとのこと。
3.飼養管理基準省令についての繁殖業者の対応状況について
- 8割近くのブリーダーが飼養施設の増設・スタッフの増員⇒数値規制に対応するための設備投資額:全体で約903億円の支出
- 繁殖引退犬や猫が、法規制もあって、手元でどうしてもあふれてしまっているブリーダーが多い。我々も譲渡活動や愛護団体と連携した里親探しをしているが、数の増加のスピードの方が上回っており、このあとの生体の居場所を作ることが到底追いついていない状況。
4.SNSなどを活用したネット販売について
- インターネット経由の消費者への直の生体販売が昨今急速に増加(インスタグラムなどSNSを使ったブリーダーから消費者への直の販売や、ブリーダー情報のまとめサイトなど)登録事業所以外での生体販売は禁止されているが、空港から遠方に生体を直接送って販売していたり、別の事業者を間にかませることで本来の登録事業所以外で販売をしている状態。
- ネット上では生まれてすぐの8週齢を満たしていない頃の写真が掲載されており、その写真をもとに販売価格がつけられている。これが、対面で販売するペットショップとの間に競争原理を働かせ、幼く小さい子ほど高値がつく市場を形成する一因となっている。
5.その他ペットパーク業界における現状の課題
●交配ルールの制定
犬や猫の交配には規制がなく、自由な掛け合わせが可能となっているが、以下の交配は避けるべき。
- ミックス犬を親にした交配⇒外貌の予測がしづらく、購入後の消費者とのトラブルが多発
- 大型犬×小型犬のような体格差の大きい交配⇒母体の負担や仔犬の成長への影響が不透明
②全国ペット協会 赤澤事務局長
1.犬猫の出生日偽装問題に関する見解
今回の出生日の偽装問題について、業界として大変重くとらえている。事業者・業界そのものの信頼・信用を貶めることであり、なによりもお客様、飼い主の皆さまを不安にさせてしまい、まじめに取り組んでいる事業者が肩身の狭い思いをしてしまうこともあり、当たり前にまじめにやっていることを可視化する取り組みを始めている。
2.取組み
- 倫理規定の策定、倫理研修会の開催、倫理委員会の設置
- 誓約書の導入(会員に誓約書へサインしてもらう。犬猫を扱う会員には「8週齢規制を守る」旨チェックしてもらい、扱わない会員は「法律を守ります」というような内容)
- あんしんペット台帳(※)の機能強化
※あんしんペット台帳について
法律で義務付けられている帳簿や台帳のためのアプリ。日々の業務の流れに沿って情報を入力するだけで、動物愛護法で義務付けられている帳簿・台帳の作成ができる便利ツールの形で開発したもの。
もともと小さな業者の利用を想定していたので、出生日の担保を取っていくことを念頭に置いて開発したものではないが、いくつか機能強化をしている。
(1)生年月日の入力制限
正しい情報でなければ入力が難しくなるように進めている。
・生年月日は生まれてから3日以内に入力しなければならない
・出産時には生まれたときの画像のデータも記録
・交配の実施記録台帳にも対応⇒お父さんお母さん犬・猫を選んで交配データ・履歴もとれる。交配日~出産日の間隔について、早産もあるが現実的にこれはないのではというラインを引く。
(2)生年月日の修正制限
万が一誤入力した場合は協会に連絡いただき理由を含めた履歴を取りながら修正をする。
利用者を増加する取り組みが大事だと思っている。もともとは会員に限って会費の中で無料で使えるサービスだったが、会員以外のショップ・ブリーダーも利用できるよう調整中。
3.移動販売について
移動販売・ネット販売について、私共はもともと2003年の「ペット小売業宣言」で反対だと表明。
そもそも移動販売は、ペットを提供する適切な体制(その場での管理、重要事項の説明、アフターフォロー)を整えることが難しい販売方法である。
4.飼養管理基準省令について
我々のいろんな業界団体は、前回の法改正後の新たな基準等について啓発を続けてきた。そのためにそれ相応の負担が生じてきた中で、しっかりやれていると考えている。一方で、自治体の業務量が増え、適切に監督するために大変な労力と時間が必要になっていると聞いている。国のほうで自治体がしっかり動けるような、悪質な事業者を是正・排除するための体制を整えていただくことが必要。
③日本獣医師会理事(動物福祉・愛護担当) 佐伯様
1.8週齢規制違反について
獣医師会としては、指定登録機関としてマイクロチップの登録情報を扱うという点では非常に遺憾。動物のことを考えると8週齢規制は非常に重要なもので、しっかり守ってもらわなければ動物のためにならない。信頼の失墜どころではない。個人的には非常に憤りを感じている。
■対応策
- 法改正後の獣医師の認識を高める
2019年の法改正で様々獣医師が関与するようになったが、まだ十分に徹底されていない。獣医師の認識も今後高めていく必要があると考えており、環境省と協力しながら進めていきたい。
- マイクロチップの内容確認の徹底
マイクロチップの内容について、例えばワクチン接種で民間の動物病院に来院された際しっかり獣医師が診察し、年齢と合致しているか確認する。あるいは愛玩動物看護士もそこに関わることで二重三重のチェックが可能ではないか。
現在、獣医師はマイクロチップの内容を検索することができないが、内容を確認することで年齢が詐称されていないか確認することにもつながるのではないか。
- 企業内獣医師の職業倫理・専門性の向上
ペットパーク流通協会さんの所でも獣医師が年齢を確認しているが、企業内の獣医師がどこまで独立して一律してそれを担保できるかというのは職業倫理にも関わる。そういった職業倫理を高めることや、こういった取扱業に関わる獣医師の専門性を高めていくことも考えていきたい。
今回の問題で疑問なのは、動物取扱責任者が取扱業者の中にいるはずなのに、この人たちはどう関与していたのかということ。動物取扱責任者は資格要件を設けているにもかかわらず、きちんと作用していないのでは。この人たちがしっかり義務と責任を果たせるようにすることも一つの手。
2.マイクロチップの装着義務化についての対応状況
ペットショップからペットを購入した飼い主に変更登録義務があるが、未だに飼い主の認識が十分でない。ここが変わらないと(登録上)ずっとペットショップの犬猫になってしまう。日本獣医師会で把握している数でいうと、かなりの頭数がきちんと変更登録されていない。ペットショップ側も変更登録ができるようにするなどし、ちゃんと変わらないと意味がない。
(2)意見交換
・獣医師会「動物取扱責任者が職責を果たしていないのではないか」
⇒(環境省)環境省の調査では、第一種動物取扱業者のなかで動物取扱責任者がどういう役割を果たしているか精査できていない。違反が多く見つかった事実を踏まえると、法令順守も含めて対応すべき責任者が適切に対応していないとしか思えない。
■全国ペット協会の取り組みについて
・あんしんペット台帳は生年月日の入力を偽装したらどうなるのか。出産時の画像データは他の子の写真を使うなどどうにでもできる。交配日を早くしたら誕生日も早くできる。交配日を早くしてあと全部ずらせばいいのでは。
⇒(全国ペット協会)交配日の入力に制限をかけていくなど、そこの対応についても検討する。
⇒(環境省)私はある程度意味があると思う。出生日を2~3週間ずらそうとすると、まだ生まれていなくても、システムに事前に頭数や性別を入れる必要がある。当然、頭数は多く入れておかないと、入れている頭数より多く生まれるとこの差分は売れなくなる。しかし、実際に少なく生まれた場合、差分は死んでしまったのかという話になり、それはそれで問題になるのではないか。
・倫理委員会で会員企業の処分とあるがどういった処分を検討されているのか。
⇒(全国ペット協会)現時点で、定款上できる処分で一番厳しいのは「除名」処分。
・除名処分は、会員に対してどのくらいダメージになるのか。罰金や何日営業停止などペナルティも考えているのか。法律でなくてもそういったことは可能なのか。
⇒(全国ペット協会)除名しても我々は任意加盟の協会なので、営業ができなくなることはない。我々の会員サービスが受けられない。次の手としてまだ確定していないが「公表」も考えている。
■オークション、ペットパーク流通協会の取り組みについて
・オークションはいくつあって、オークションを通る動物はどのくらいいるのか。その裏にブリーダーがどのくらいいて、業界的に守らなそうな人はどのくらいいるのか裏側を教えていただきたい。
⇒(ペットパーク流通協会 上原会長)年間約40万頭がオークションを通っている。我々の加盟店が15あり、40万頭のなかで約44%が我々のパークかと。加盟していない大手に加え、小さいがオークションをしているところが5~6件。オークションの数は全部で19~20件だと把握している。(※Evaコメント:なお、令和5年4月1日時点では29件。参照:動物愛護管理行政事務提要(令和5年度版))
ブリーダーのうち、大体21%が加盟していないパークでやっている。大体63~64%のブリーダーが我々のペットパークの流通の中にいると思う。
SNSでの販売量は17%ほどある。それが約6万頭弱。ブリーダーが直接販売しているのが約11%、ブリーダーが親戚にあげたなどが約6~7%が流通過程。
うちで360回オークションを開催したなかで、体重を測らないと出品できないので、そのときの全犬種の体重を測って出た値について、大体1週間偽装しているだろうという数値をもとに7日間で割った体重を加算した数字を品種別出品不可体重としている。超小型犬は400g未満、小型犬は500g未満、中型犬は700g未満、大型犬は1,200g未満、超大型犬は1,500g未満。ミックス犬は母犬の小さい方のサイズに合わせている。
また、日齢偽装注意喚起後の出荷状況(2024/2/21~3/29)を調査し「サイズ別の出荷体重の推移」や「開催日別の生年月日の分布」をグラフ化した。(※Evaコメント:生年月日はオークション開催日のちょうど57日前に生まれた頭数が明らかに多い。環境省による調査結果の公表(2/15)後もなお8週齢規制違反が改善されていないことが疑われる。)
例えば、ゴールデンレトリバーだと8週齢を守れば価格が3万円で、守らないと15万円という格差がどうしても出る。7週齢から8週齢になったときは、最初は守られていたが、自治体も注意しないので、だんだん高値がつくほうに流れてしまった。我々が指摘しても「この犬種については守れているが、まだ門歯が生えていない」と言われるとそれ以上踏み込んだ指導ができなかった。どうしても生年月日が開催日にあわせて偏ってしまう。このグラフを毎回毎回オークションが始まる前に皆さんに説明して、こんな数字になるわけないじゃないかと厳しく言っている。
4月13日に全国のメインどころのペットショップに集まってもらい、こういった数値がどうすれば守られるか話したい。買う側のペットショップに協力をいただくことが一番最優先の問題。大手はいろんな人から見られているので対応が早いが、問題なのは大手と戦わなければならない小さなペットショップ。ここはなかなか変えようとせず、かえって「これはいいチャンスだ」と思うといけないので、今回小さなペットショップをメインに指導する予定。
・出品不可体重について、小さな子もいるし大きくなる子もいる。どう考えても個体差や発達の速度が違うと思うが、今度はそういった子がはじかれてしまうことにもつながりかねない。体重を目安に8週齢を規制していくのには限界があると思うが、そのあたりはどう考えているのか。
⇒(ペットパーク流通協会 上原会長)出品不可体重は大体の目安で、この体重に達していないから出さないということではない。それには担保として、獣医師の診断証明書を添えてもらう形で個体差については対応する。
・今の繫殖引退犬・猫の問題として、糞尿の失敗、環境音や人におびえ慣れていないことが多く挙げられる。疾病を抱えている個体もそのまま出てくる問題もあるので、いま繁殖に使われている個体にはしっかりと対策を講じていただきたい。8週齢の偽装は、このままだともしかしたら幼齢個体の販売禁止という流れになっていくのではというような非常に由々しき問題だと思っている。
⇒(ペットパーク流通協会 上原会長)おっしゃるとおりで、うちも引き取ったときにそういうことや犬に名前が付いていないこともある。自分たちが手放すことを考えて飼育をするようブリーダーに指導している。
・規制や罰則のない別オークションに流れて買う人はどんな人なのか。そちらを取り締まらないと、いたちごっこが続くのでは。ごまかす業者に対しては法律的に今どういう対応になっているのか。
また、オークション側としては、どんな取り締まりが念頭にあるのか。
⇒(ペットパーク流通協会 上原会長)取組としては、日本獣医科学大学にブリーダーを回っていただき、全体の20%はやめさせるなど厳重に注意する必要がある。本当に優良なブリーダーは一握り。ただ、60%以上の人は教えれば改善する意欲が強いので、どう指導していくか大学と検討している。
この20%の人が、例えばインボイスやマイクロチップなど我々も1年くらい教えたが、手が回らないので「自分たちはもうすぐ辞めるからインボイスいらない」とか「マイクロチップつけなくてもいいんじゃないか」と言う。
買い手(ペットショップ)にモラルを守らせることが一番早い解決方法。「なぜうちより小さいのを売っているんだ」とブリーダー同士で指摘するようになってほしい。ペットショップも「なぜあんなの買ってくるんだ」と、モラルや考え方をやっていかないと業界側も信頼されないよということを強く発信することだと思っている。
⇒(環境省)現行法に基づくと、8週齢規制違反をしたことが確認できれば自治体から勧告・命令の対象になる。命令にも従わなければ、罰金刑、登録取り消しの対象。ただし、これはあくまで8週齢違反が確認された場合。今回の一斉調査でも、自白等により8週齢違反が確認できたが、違反しているが自白がなく確認できていないブリーダーがいてもおかしくない。そういう者に対して行政処分ができるかというとすごく高いハードルがある。
また、曜日の偏りに関して、今回のことでもっと賢くごまかされてしまうとよくないと思っている。オークション開催日の57日前にみんな出生日をあわせていたからこの情報が見えたわけだが、58日、59日、60日、61日前とずらしていれば何もばれなかったので、それでグラフが標準になったということがないよう、しっかり対策をする必要がある。
■移動販売について
・移動販売の問題は、幼齢個体の輸送ストレスや環境の変化が非常に大きいことで、これはペットショップに連れてこられる個体についても同じことが言える。オークションの会場によっては当日連れてくるのではなく、1~2泊、長い時は3泊する個体もいる。オークション自体の規制も必要で、そうすることで悪質な、何も対応していないオークションに流れることに歯止めが利くのでは。
⇒(ペットパーク流通協会 上原会長)うちは地域密着型のパークなので、地域の方が会場に持ち込むのがほとんどで約90%。ただ約500頭は地方からの送りで車で送迎に行く。うちで送迎しようかと言うと「そんなの心配で預けられない」と言うブリーダーがいるのが現状。輸送でできるところが我々からしたら考えられない。ただ出品頭数が多ければ多いほど、大型犬も小型犬も注文の犬も買えて利便性が良く、そこは自分たちも力足らず。今の意見を聞いてますます地域を大切にしようと思った。
・移動販売について、獣医師会さんのご意向・ご意見をお伺いしたい。
⇒(獣医師会)獣医師会として対応はしていない。個人的にいろんなことを知るために見に行くことがあるが、ひどい。皮膚の状態が悪かったり目に傷があったりする犬が平気でいる状態で、輸送される動物のストレスも大きいので、そういったことはやめてほしい。前回の法改正で、輸送した後2日間は目視で動物の状態を観察しなければならなくなったが、目視に過ぎず、誰がという規定まで具体的にないので、そこは取扱責任者と定めてしっかり確認させるなど、せめて規制を強めるべき。
・移動販売において2日間の目視の実効性は担保されていない。車の中など実際に販売する環境とは違うところに置くことでむしろ個体に負担をかけている。やはり移動販売は廃止するしか方法はないが自主的に移動販売しないとなっても法規制は必要だと思うので、出店規制はしていただきたい。
・ペットパーク流通協会に入っていないオークション会場の獣医師の名前が、移動販売で買われた犬猫のワクチンの証明書に出ている。やはり劣悪業者に協力する獣医師がいる。獣医師が関わるからといって安全ではないと思っている。
・海外だと移動時の規制などがあるが、獣医師会ではどのくらいの距離で休憩を取るべきかなど決めているのか。
⇒(獣医師会)移動販売に特化した検討はしていない。獣医師の信頼性という点はおっしゃるとおりで、そういう獣医師がいることは我々も問題だと思っている。できる限りのことはやっていきたい。
・ペットパーク流通協会のヒアリングで「移動式販売を実施しているのは2社で、移動式販売の終了は既に考えている」とあるが、議員連盟として「移動販売の禁止」を打ち出してもよいか。ネット販売と移動販売の禁止を思い切って打ち出したらどうかと思うが、ご意見は。
⇒(ペットパーク流通協会 上原会長)移動販売については、環境省や太田記者から「移動販売やめるよう指導しなさい」と以前から話があり、やめるよう言ったが、うちじゃないオークションから買えてしまう。群馬の方にはやめると言っていただいている。山梨の方は業界からやめろと度々言っており、そう長くないうちにやめると思う。繁殖に力を入れていて、自分たちでショップ展開している。
ネット販売の1番の問題は、生後2週間で定価を付けること。ショップもより小さい子が欲しいという作用が働き、悪の根源になっている。我々は仕入れた時に目の傷、足が弱い、心雑音があるなど検査したうえで、査定で10万15万とつけるが、ネットでは30万40万という値段がつけられているのでショップが焦っている。
⇒(全国ペット協会)ネットの販売も、対面での説明や現物確認が必要なので、実質的には単純な通信販売はない。今の基準の中にも、過度な愛らしさを強調した広告はダメとあるが、広告の規制は慎重にしないといけない。ネットが使えない影響は何かしらあるかもしれないので、十分検討が必要。
■その他の意見
・希少種でも国際希少野生動物種の登録票があるが、売っている個体に違う登録票がついてることがずっと起きている。個体の同一性の担保は非常に大事。もう少しシステムは詰める必要がある。
・業界の努力として、血統書の発行を、例えば生後1週間以内としていただくのも1つの方法。現在、血統書の発行は生後90日以内までで、90日過ぎてもお金を払えば発行できる場合もある。ここが出生日を偽装できる1つのチャンスの場。現状、オークションに出荷するときに出生日を偽装し、その後偽装した出生日で血統書を登録している。
⇒業界内で生後1週間以内に血統書登録・発行を義務付けると、先に血統書の誕生日が確定してオークションに出荷する流れになり、偽装の場が限られてくるのではないか。
第7回 動物愛護法改正PT(2024.03.18)
(1)動物取扱業の適正化(飼養管理基準省令施行後の現状と課題、8週齢規制の現状と実効性強化の在り方、その他法改正を要望したい事項)について関係者ヒアリング:
①朝日新聞記者・太田様
詳しくはこちら(3/30朝日新聞)
■飼養管理基準省令施行後の現状と課題
●自治体の状況
- 飼養管理基準省令がどのくらい守られているかは、立ち入り検査をしない限り不明。
- 省令に適合していなかった業者がいた自治体は103。4997事業所に対して指導が行われた。そのうち「勧告」まで進んだのが19事業所、「命令」の行政処分はわずか4事業所。
- 1つの事業所に対して3回以上指導(※指導:法的根拠なし。口頭・文書で伝えるだけ。実行力なし。)を繰り返すだけの自治体が、51自治体もある。
- 小泉元環境大臣がレッドカード基準にする、と言って導入した飼養管理基準省令の本来の目的がまだまだ現場においては浸透していないし、達成できていない。
一方で、こんな自治体の声も多くあった。
- 「指導が徹底できるようになって犬猫の飼育環境が上がっている」
- 「安易な動物取扱業の登録申請が減って入り口での抑止効果がある。」
- 「基準に対応できないことが理由と推察される業者の自主廃業が確認されている。」
全国31自治体で省令の施行により廃業した業者があった。⇒基準を満たせないことで廃業した業者がいるという意味では、悪質な業者の淘汰ができている可能性もある。
●飼養管理基準省令施行後の課題
- 運動場に3時間以上出しなさい、という部分は確認のしようがない。
- 移動販売が1番の問題。指導している間に立ち去るため、問題点を指摘しても改善する前に事業者がいなくなる。
- 緊急保護ができないので虐待されている動物をきちんと救えていない。
- 従業員1人当たりの飼育頭数に引退した繁殖犬猫を含めていないため、ほとんどの業者が複数頭の繁殖引退犬猫を飼養しているなか、適切に取り締まれず、抜け道になっている。
- 純血種の放浪⇒「業の登録取り消しまで進んだ場合、その事業者が飼育する犬猫が路頭に迷うため、動物愛護団体との協力が不可欠。そのスキームモデルを示してほしい」との意見も。
■8週齢規制の現状と実効性強化の在り方
●8週齢規制の実効性について
2023年12月の調査で、8週齢規制の実効性について各自治体に聞いた。
- 順守状況の確認はきちんとしている(1自治体を除く)。うち82自治体が、4種類以上の手段を用いて確認しているが、実効性が高いと評価する自治体は2自治体のみ。
●オークション会場の問題
環境省の調査(令和6年2月15日発表)からも分かるように、オークションの場が出生日偽装の舞台になっている。オークションに対する厳しい意見も自治体から寄せられた。
- オークションに出生証明などの確認を義務付けるべき
- 最終的にはオークションの廃止が必要
一方、オークション業を行う関東ペットパークでは、会員へのサービスとして「出荷可能月齢票」を配っている。これは、例えば「このオークションの開催日に出荷できるのは12/26生まれ」というような開催日ごとの出荷可能な出生日が記載された早見表。だがオークション側がこのようなものを繁殖業者に配ったら、この開催日に出荷できるように誕生日を偽装してしまう。
●繁殖業者が犬猫の出生日を偽装する背景
飼育コストの削減及び消費者が仔犬仔猫を好んで買い求める傾向があり、結果として小さいうちに出荷したほうがより高値で売れる業界特有の事情がある。このあたりは、自治体もよく理解していて、意見が相次いだ。
- 消費者への啓発が必要である
- 超小型または未熟な仔犬仔猫は身体が弱い傾向にあり、飼ううえでリスクがあることを購入者に普及啓発するべきだ
●8週齢規制の実効性を強化する方法について
地方自治体からの意見としては、
- 獣医師による出生証明書の義務付けが必要
- 犬種ごとに体重で線引きすべき
- 販売禁止期間を延長すべき
1.獣医師による出生証明書の義務付け
恐らく獣医師法の改正が必要であるかとは思うが(※診察をしていない個体の診断書は書けない為)地方の繁殖業者は近くに動物病院がないこともあるのでウェブ診療できるようにする。
2.犬種ごとに体重で線引き
大手ペットショップチェーンでは、ブリーダーの出生日偽装が分かっているので自衛手段として、独自の最低体重の基準を設けているところもある。
- 全国150店舗を展開するPetPlus(ペットプラス)…トイプードルやチワワであれば450g、ペルシャ猫であれば600gなど、それ以上の体重でなければ、たとえ繁殖業者が8週齢規制を守っていると言っても仕入れないことにしている。⇒この基準体重自体すごく低い数値。トイプードルは8週齢規制を守っていれば1㎏はある。猫を600gで出荷したら大変なことになる。
- ペットショップのコジマ…健康管理センターを新設し、仕入れた仔犬仔猫をセンターに1週間程度留めている。繁殖業者が犬猫の出生日を2~3週間ごまかしているのであれば、せめて一定期間センターで健康状態を見極めてから販売するという取り組みをしている。
ペットショップチェーンからの意見としては、
- 1番ごまかしにくくなるのは、交配日を写真付きで行政に報告し、生まれたときに写真データで再度行政に報告する方法。
それに加えて、犬や猫は交配日から出生までの日数が大きくずれないので、出荷時のデータなどをリアルタイムに行政に報告し、行政で確認できる仕組みを導入してはどうか。
■その他、法改正を要望したい事項
- 8週齢規制に日本犬6種が適用除外になっているのはおかしい(56自治体)
- 移動販売の禁止が必要(58自治体)
- 犬猫等の繁殖業者に対する許可制の導入(41自治体)
- 緊急一時保護制度の導入(51自治体)
実際に導入・運用する段階になれば、自治体の労力の問題も出てくるにもかかわらず、自治体からの要望も多いことは大変心強い。
●その他の問題について
- ミックス犬の乱繁殖。⇒純血種については、JKCが6回以上の繁殖・交配をしていたり、7歳を超えて交配している母犬から生まれた仔犬については血統書を出していないので、実行性が担保できているが、ミックス犬は血統書がないのでごまかすことができている。
- 実質的なネット販売の横行(近隣引き渡しサービスやブリーダープラスなど)⇒ネット販売を禁止した際に代行説明業者が横行したため、前回の法改正で”販売する事業所”において現物確認・説明を義務付けたが、それを違うやり方でやっている。例えば、"みんなのブリーダー"はブリーダーから施設に仔犬仔猫を移送して、消費者がその施設を訪問して購入する形で実質的なネット販売をしている。施設が仕入れて販売するという建付けは非常にグレーで、立法の趣旨を損なったサービス。
- SNSを活用したネット販売。秋葉原では中国人が犬の箱を持ち、その場で引き渡しているという場面も見られている。
- 第1種と第2種動物取扱業者の垣根が曖昧になっている。
●犬や猫の流通量、繁殖から小売りまでの過程における死亡率
毎年、朝日新聞で流通量を調べている。コロナ禍でかなり売れた反動なのか、2022年度に初めて流通量が減った。犬の死亡率も、法改正の影響か年々右肩下がり。
一方で、猫は流通量は減ってきているが死亡数が右肩上がりのまま。猫の飼養管理について犬ほど研究が進んでいないところもあり、猫についての飼養管理基準も見直す必要があるのではないか。
②アニコム損害保険(株) 取締役会長執行役員 小森様
まず、我々は法令を守っている会社に金融サービスを提供すべき立場で、法令違反を未然に防ぐ社会的な責務がありながら、業界に法令違反が蔓延し続けていることを業界に関わる金融機関として深く謝罪したい。犬の10%はアニコム保険に入っている。ほぼすべてのペットショップ、動物病院、ブリーダーのところに出入りをして、場合によってはお金を貸し付けたり、投資をしたりする立場なので、ほぼ何らかの形で資本関係がある。
■飼養管理基準省令施行後の現状
※当社における現状の認識を示したもの。概ね順守していると思われるものは とする。
とする。
 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造と規模と管理(ケージ,運動スペース)
飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造と規模と管理(ケージ,運動スペース) 従事する職員の数⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」
従事する職員の数⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」 環境の管理(温度,清潔,光環境)⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」
環境の管理(温度,清潔,光環境)⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」 年に1回以上の健康診断
年に1回以上の健康診断 展示・輸送の方法(目視観察)⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」
展示・輸送の方法(目視観察)⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」- △繁殖に関する規定(6歳6回)⇒確認が困難
 動物の管理に関すること(生体の衛生管理,運動,ふれあい)⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」
動物の管理に関すること(生体の衛生管理,運動,ふれあい)⇒大規模は「順守」、小規模は「不明」 幼齢の犬・猫の販売等の制限(8週齢規制)
幼齢の犬・猫の販売等の制限(8週齢規制)
1頭当たりの飼育面積は見ればわかるから守られるが、8週齢規制や出産回数が6回以内かについては確かめる術がなく守られていない。
ショップやブリーダーは法令を遵守していない"恐れがあると思われている"という程度の認識しかない。刑罰はなく過料だが、違反していることをもっと強く指摘するべき。
●8週齢規制の意味合い
業界は「そもそも8週齢規制自体がおかしい」、「8週齢規制はまともなデータに基づかず立法事実がなかった」と言うことがある。本規制は”守ることに意味のある”規制なのかどうか分析が必要。
この観点から、当社の保険診療の統計データで分析したところ、幼齢販売ほど傷病率が高いことが分かった。6週齢くらいだと最も保険金が高く、8~9週齢になると保険金が目一杯下がる。⇒8週齢規制の立法事実が確認された。
●ペット=今や必要不可欠な社会的存在
テクノロジーの進歩により人間関係から自由になり、1人で生きていけるようになったことで国民を孤独の刑にした。孤独という害悪に対してカウンターバランスを果たしているのがペット。ペットには申し訳ないが、人間の文化が進化すればするほどペットがカウンターバランスを果たすことになる。ペットがいれば生きる気力がわき、ペット業界がない国は国民が病んでGDPが落ちると考えている。
●日本が動物愛護後進国と言われる根本的原因
- 日本は8週齢以下で販売 ⇐幼齢であるほど可愛い
- 幼齢販売は衝動買いを促し、合理的な意思決定を捻じ曲げる
- その結果、飼い主とのミスマッチが多い
⇒日本は諸外国と比較し、殺人事件や凶悪事件が少ないにもかかわらず、動物虐待・遺棄・殺処分は多い。日本が動物愛護後進国と言われる根本原因の1つが、8週齢違反による「衝動買いの横行」。
●なぜ守られないのか?
- 無謬性の原則(=特に業規制は必ず守られるべきという考え方)⇒規制の担保が必要
- 日本の特殊性=なんでも水に流す島国の日本、環境問題にも無頓着。
- 業界の自主規制⇒省令導入に際し「実効性の担保に課題あり」とする委員側と「自主規制で対処できる」とする業界団体側で議論した結果、自主規制を信じ、規制の担保なく制定された。
- 「業規制」と「一般規制」 ⇒法令には、特定事業者に遵守を要請する「業規制」と、国民全員が遵守すべき「一般規制」がある。しかし、業界内で起きていることを外部の者が知ることは極めて困難。一方、消費者は事業者が法令を遵守していることを信じて経済行動を起こす。 ⇒社会全体の円滑な行動を確保するために「業規制」の遵守は絶対的に必要。
規制の担保がなく、帳簿の備え付け義務も課されなかった(※Eva訂正:帳簿の備え付け義務は規定あり【動愛法第21条の5】)。基本的に生体は幼いほど高額で販売でき、お世話の期間も短いためコストも安い。加えて、他の事業もやっている以上、自分もやらないと損をする状況。⇒守った者が損をする、いわば「正直者が馬鹿をみる」状況。
■再発防止策
1.56日間の適正な生育記録(※)を義務付ける ※犬に限らず、生まれてから離乳までの期間で最も重要な指標となるのは「体重の推移」。「体重推移」と「顔写真等」による成長過程を記録した帳簿の備え付けを義務付ける。
⇒AIによる自動登録 産室のカメラ画像でAI学習を進め、親犬・仔犬の検出が一定程度可能な状況にし、システムへ自動登録できる機能。カメラ画像とシステムを連携させ、カメラに捉えた親犬・仔犬の名前、交配日や出生日、外貌から推計した体重をシステムへ自動登録することができる。カメラ画像にはタイムスタンプを付け、偽装を防ぐべく事業者での設定はできないようにする。
2.ガイドライン(体重等)を設ける
当該事業者以外の関連事業者(ペット保険会社,動物病院)と国民に対し「歯列」「基準体重」「行動特性」等知識を周知し、衆人環視の状況にすることで”違反の検出”を目的としたけん制体制を構築。
3.法令面での手当 「帳簿の備え付け義務」や「ガイドラインの使用」を省令(通達)で定める等の、政府介入サポートが必要。以下を動物愛護法施行規則に入れ込むことにより政府介入サポートの実現が可能。
- 出生後56日を経過するまでの日次の生育を記録すること。
- 上記の記録を改ざん不可能な電磁的記録媒体を用いて事業者が証明すること。
(2)ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査の結果について環境省ヒアリング
令和6年2月15日発表のとおり、ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査をした。結果、ペットオークションに関しては現物1個1個を確認したわけではないが、生年月日の改ざんがなされていることが強く疑われた。ブリーダー1,400ほど(※登録されているもののうち1割くらい(令和2年4月1日現在 繁殖業者数:12,949)にあたる)のうち半数が何らかの法令違反あり。※法令違反は「帳簿の不備」や「帳簿がないこと」も含めたもので、すべて「8週齢規制に違反していた」というわけではない。調査着手のきっかけの1つが、マイクロチップの登録情報を確認したところ、一定数のブリーダーにおいて犬の生年月日の曜日に隔たりがあることが判明したため。
今後、我々からも法令を守るように指摘していくが、ペット業界は1枚岩ではなく、全体を見ている協会があるわけではないことを踏まえ、何らか実効性のある形で改ざん防止策を検討中。
(3)意見交換
■犬猫の販売規制について
・遺伝疾患のある犬猫あるいは重篤な遺伝疾患発症の恐れがある種で未検査の犬猫の販売規制 遺伝性疾患のある親犬猫を繁殖に供さなければ良いが、現状自主規制だけでは担保されず、対応策の生体補償(同犬猫種と交換)は命の倫理に反する。
・動物飼育不可の住宅に居住している者への販売規制
動物飼育が禁止されている住宅居住者への販売は事前回避が可能。
■ペット業界の自主規制について
・最初は基本的にどの法律であれ自主規制に任せるのがスタンダード。ペット業界がどのような自主規制をしてきて、どういう実態があってどうアクションしたのか。
⇒(小森様)我々の業界は自主規制すると宣言したが、結果として法令違反者が儲かっている。幼ければ幼いほど高く売れるので、自主規制は無理。本来無理なことをすると言ったことは反省している。でも反省すべきなのはペット業界だけではない。業規制は情報の非対称性があるので、議員立法が成されるときに規制の担保を入れなかったことが最大の問題。
⇒(太田記者)議員立法全会一致のプロセスを振り返ると、8週齢規制が実現するかどうかが、最終的に日本犬が適用除外されたように非常に瀬戸際で政治的になってしまい、その方法論まで踏み込めなかった。業界側からすれば「守ることが担保できない法律を守れと言われても」という側面があることは我々もわかっている。そもそも業界は「8週齢規制によって5~6割の業者は廃業することになる」と言っていた割には廃業していない。業界の宣言や自主規制は信用していないから規制が強まってきたプロセスがある。
⇒(小森様)はじめはみんな守ろうと思っていたが、徐々に抜け駆けが増えて守られなくなった。業界にガバナンスがあれば守っていない人を通報できたが、我々の業界は仲間意識が強くてガバナンスがない。おそらく1~2割は守っている事業所もいて、正直者が馬鹿を見るという議論は常にあったが、結果的には私的利益の追求にその声はかき消された。
■環境省の取り組みについて
・8週齢規制は前回法改正の肝でもあり、守られていないのは1日も早い是正が必要。環境省は実行力のある対策を考えているのか。 ⇒(環境省)最も実行力があると考えているのは、頭数も含めて出生日を公表させること。「生まれた日(あるいは生まれて〇日以内)に必ず何匹、種類、雄雌などを公表」させれば一番コスパが良い。
⇒(太田記者)関東ペットパークは、自主規制として「あんしんペット台帳」を付けさせて、生まれた日と5日ごとに体重と写真を登録しないと出荷させない仕組みを検討中。しかし、これを嫌がり、ごまかそうとする劣悪なブリーダーは別のオークションに売りに行くだけで、関東ペットパークがいくら頑張っても実効性はない。でもオークション側ができる最低限のことをやろうとしているので、せめて出生日から5日ごとに体重付きで行政に報告させるべき。かつ、守っているかどうかは、今のように帳簿が業者にあるままだと行政が立ち入り検査しない限り確認できない。デジタルの力で行政側にデータとして取らせる仕組みが必要。
・環境省の調査について、個別にブリーダーに対して勧告等の指導監督を行ったとあるが、オークションに対しての指導は行っているのか。
⇒(環境省)彼ら自体が法令違反したわけではないので、法令に基づいた指導等は現状できていない。
⇒(塩村議員)指導の法的根拠はないのだろうが、オークション側も、どう見てもおかしい仔犬仔猫をどんどん出している責任はある。オークション側の指導も考えたほうが良いのでは。
⇒(環境省)当然それは我々も分かっており、オークション側にも問題があると話はしている。
⇒(小森様)飼養管理基準省令第2条第7号リ・テによると、オークションもペットショップもブリーダーが法令を守っているか確認する義務があり、罰則はないが省令違反。ただ、オークション側は両方(ペットショップとブリーダー)に良い顔をしたい。もしかしたらショップより法令順守意識が低いかもしれない。
■その他質問・意見
・なぜペットオークションで取引しないといけないのか。そもそも流通量が多すぎる形成になっていることに違和感がある。ペット市場は、生体が移動するところは意外と規模が小さく、食事や保険・衛生管理・グッズのほうが市場としては大きい。大量に産ませてしまうから、そこにばかり力が集中する。市場として提供されるべき適正な生体数はどのくらいか。
⇒(小森様)適正な生体数というのは難しい。カナダ:60%世帯、フランス・ドイツ:40~50%世帯、日本:3分の1世帯で飼育されている。孤独で悩むことが国際的問題だとすると、誰かに愛される、頼りにされることを求めるなら、流通量は今の2倍は必要だと思う。
なぜオークション会場が必要かというと、トレーサビリティを切るためだと思う。例えば犬猫に遺伝病があることが販売から数年後に分かり、病気を知っていて販売したことを罪に問われると、今のペットショップやブリーダーには損害賠償額を賄える資力はない。だからトレーサビリティを切るために日本特有のオークション会場が根付いたと考えるのが妥当。
・そもそも生体販売をなくしてほしい。獣医師でも7~8週齢の区別ができないと話すなかで、微妙な8週齢というのがごまかしが生じる原点になっている。販売できる年齢を生後6か月にすれば、たとえごまかされても犬猫の健康にも問題は起きないし、衝動買いも起こらない。
⇒(小森様)6か月にするとペットを飼う人が減るのではないか。日本は孤独な人が多くペットの支えがないと日本の活力を失う可能性があるので、6か月には反対。
今回、8週齢を守って衝動買いをなくすように業界を変えていくと宣言したい。ブリーダーを締めつけても、年間25%入れ替わるので根本的には変わらない。ブリーダーから買い上げるペットショップが法令を守らないといけない。そのペットショップは生体販売だけでは生きていけず、フードと金融商品である保険の手数料で儲けている。なので、省令通達の規制担保があるまでは、我々保険会社が経済的な自主規制を行い、8週齢を守らないショップには代理店手数料は払わないし代理店解約をする。ただ、当社だけがすると正直者が馬鹿を見ることになるので、周りの様子を伺いながら判断したい。
・販売年齢の引き上げ。母子を保護して里親に出している保護団体によれば、自然の親離れは3ヶ月程で、その頃に譲渡に出しているそう。早くに親と引き離すのは問題。
・生まれた日を公開させても偽装するのでは。
・移動販売の禁止。入荷されてから健康状態をチェックする期間が短すぎる。動物園でさえ2週間くらいかけて感染症がないか確認しており、犬猫も仕入れたら2週間程度は出荷できないようにするべき。特に移動販売は、弱い状態で仕入れて死ぬ前に売っているので問題がある。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 第17回総会(2024.02.29)
(1)会長挨拶(逢沢一郎議員)
国民の動物愛護に関する関心が日増しに高まっていることは国会議員の先生方も感じていることだと思う。本日の議題は盛沢山ですが、改正動物愛護法の施行状況を確認することがまず原点だと思っている。次なる改正に向けてどんなアジェンダをどう整理するか議連としてしっかり取り組みたい。
2、3週間前のNHKおはよう日本で、繁殖引退犬のその後について長い時間放送があった。メディアもこういう角度から関心を持ち、取り上げてくれて大変ありがたいと感じながら観ていた。
それぞれの地域で地域猫活動、TNR活動がなされている。私の地元岡山でも非常に盛り立てている。私事ですが、地元の講演会事務所をTNRの作業場として、地域の皆さんが軽トラで連れてきてくれて
1日で100匹程度のTNR活動を4~5年続けている。あらゆる活動を展開しながら殺処分ゼロを目指し、また大きな意味でのアニマルウェルフェアの環境を整えていくことを努力していきたい。
元旦は能登で大きな地震があった。ペットと共に避難を希望される、実行に移された方もたくさんおられたと話を伺っている。自治体の様々な支援やペットと共に避難ができる環境づくりには、現場での町長や市長の認識意識が非常に大きく作用するという現実がある。そういったことにも関心を持ちながら議連の活動を続けていきたい。
(2)動物愛護法改正PT進捗状況の報告(福島みずほ議員)
2023年7月まで「動物愛護法PT」として計14回開催し、次期法改正に向かうべく8月から「動物愛護法改正PT」に切り替え、計6回議論。
今後は、第7回~14回までを予定している。動物愛護法改正への検討をPTで精力的にやっていき、積み残しの課題もあるが、夏頃までにはヒアリングを終了し、来年の参院選前には改正案を提案できるように頑張っていきたい。
 (これまでの議論内容は、過去のレポートをご覧ください。)
(これまでの議論内容は、過去のレポートをご覧ください。)
(3)ノイヌ・ノネコPT進捗状況の報告(串田誠一議員)
多くの方からご意見が寄せられ、議連としても議論すべきということで昨年発足。これまでのPTで広く議論され、問題点や検討課題がたくさんある。特に簡易計画は希少種の保護が立法事実だが、その立法事実が十分に証明されていないという意味で因果関係が取りざたされている。
「ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン」は、1年施行がずれ、今年の1月から施行された。この計画でも屋外のネコを捕獲することになっているが、これによる殺処分を防ぐため個人や保護団体に依存しており、奄美大島同様、命をある意味人質のようにして保護団体や個人が身を削りながら一生懸命に命を守っているのが現実だ。行政が無責任すぎるという意見が多数寄せられている。
ノイヌ・ノネコに関しては鳥獣保護管理法に省令で規定されているが、動物愛護法第44条第4項には「ネコ」と書かれているわけで、愛護動物であるにもかかわらず、鳥獣保護管理法の対象するのは法体系的に問題ではないかという指摘もあった。
今後は、捕獲して殺処分にするのではなくTNR活動を充実させるべきではないかということで引き続き検討する予定。
 (これまでの議論内容は、過去のレポートをご覧ください。)
(これまでの議論内容は、過去のレポートをご覧ください。)
(4)改正動物愛護法の施行状況の報告(環境省)
■能登半島地震におけるペット対応について
■8週齢規制に関する調査と今後の対応方針について
 環境省(ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について)
環境省(ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について)
■マイクロチップ事業について
改正手数料は以下のとおり
- 登録及び変更登録(オンライン申請) 400円( 300円)
- 登録及び変更登録(紙申請) 1,400円(1,000円)
- 再交付(オンライン申請) 300円( 200円)
- 再交付(紙申請) 1,300円( 700円) ※括弧内は現在の手数料
(5)講演「次期改正に向けて期待する」(浅田美代子様、杉本彩)
(浅田様) 次回は、とにかく緊急保護ができるようにしていただきたい。虐待やネグレクトがあったときに所有権の問題で保護ができない。個人の多頭飼育崩壊も増えている。助けたくても助けられない状況。
前回の法改正で8週齢規制などを通してもらったが、結局何も変わっていない。行政はそこも含めて対応してほしい。行政に通報しても人員不足を理由に現場に行ってくれない。行政が対応できない理由は「人員が足りないから」とよく言われる。であれば、一般の方で動物愛護に精通している人を派遣してイエロー・レッドカードを出すなどの制度を設けることを検討してほしい。やってほしいことはいろいろあるが、まずは緊急保護ができるようにすることを強く要望したい。
(Eva杉本) Evaが刑事告発をして2年間裁判が続いた、長野県松本市のアニマル桃太郎という繁殖事業者が、獣医師免許なく無麻酔で多数の犬のお腹を開いて仔犬を取り出し死に至らしめたり苦しめていた事件。先日検察の求刑が出たが、たった懲役1年、狂犬病予防法違反で10万円の罰金。ほぼ100%実刑になることはないと思います。
これだけの事件でたったこれだけの求刑というのは、とてもじゃないけれど厳正に裁かれているとは思えない。議員の先生方のご尽力によって動物虐待罪が厳罰化されても、司法の場にもっていくと厳正に裁かれないということが本当に悔しい。司法の場でこういう状況になるなら、やはり事件化される前にきちんと行政のほうで業の管理、指導をやっていただき、問題のある事業者に対しては勧告・命令をして業の取り消しをしていただく、事件になる前にきちんと防いでいただくしか術がないんじゃないかと思う。
環境省のみなさん、業界に対して一斉調査をしていただき本当にありがとうございます。大変感謝しております。今までメディアでは「悪質な一部の事業者」という表現をよくされていたが、この調査によって、一部の事業者じゃなくて大半の事業者が悪質な行為を行っていたということが本当によく分かったと思う。マンパワー不足や予算不足などの言い訳を自治体にさせないよう、管理監督をして、業の取り消しまでステップアップして持っていくことを徹底的にやっていただくしかもう術がありません。なので次期法改正では、こういった悪質な業が横行しないように、事業所に獣医師を常駐するなどの規制を設けることなどが必要だし、行政が動けるような体制をどうつくるかということもぜひ皆さんのお知恵をお借りしてご尽力いただき、これ以上悪質業者が横行しないところにまで徹底的にもっていっていただきたい。国会議員の先生方にも期待しております。
(6)その他の報告(動物愛護法改正に向けてSNSを使った意見募集の結果報告)
1.実施方法 グーグルフォームでの配信
議連メンバーの議員室、動物愛護市民団体、関係自治体に配信し、拡散も依頼
2.実施期間 2023年7月28日開始~9月30日締切り
3.回答件数 12,022件
4.アンケートの依頼内容
「要望事項」「要望事項の説明」「団体・個人の種別」「回答者の属性(年代、住所地域)など」を記入し、回答を送信してもらった。
5.アンケートの主な要望内容
 「生体販売」の禁止
「生体販売」の禁止
いきものを金銭で売買すると言う行為に、さまざまな価値観や情報をきちんと共有出来る現
代におよそ考え難い倫理観の低さを覚えることに加え、いきものと生涯共に暮らすことの責
任感を著しく低下、省略化する愚行と考えるからです。是非ご一考をお願い致します。
 動物虐待への厳罰化
動物虐待への厳罰化
猫や犬が毒殺されていても警察は全く動いてくれない。罰金払えば済むだろうという安易な
発想がある。2020年に厳罰化されたが、依然として罰せられることがあまりにも少ない。人
間と同じように捜査、逮捕、重い実刑を望む。
 ブリーダーの国家資格制、飼育者の資格取得制
ブリーダーの国家資格制、飼育者の資格取得制
ブリーダーや販売店舗従業員の免許制にすることで悪質な販売業者を締め出す。飼育責任者の能力を高めること。資格の取得制によって、気安く購入する者・販売する者を規制できる。
 動物の所有権剥奪
動物の所有権剥奪
不適切飼育をする飼い主から動物の命を守るために、「モノ」扱いである動物の所有権を剥奪
することが必要。また、不適切飼育や虐待飼育をする飼い主に、永久に動物の飼育を認めない
法律も必要。
 殺処分の廃止
殺処分の廃止
保健所で保護した動物の殺処分を廃止し自治体とボランティアが連携し最後まで保護すべき。保護された罪のない犬猫が1週間程度で殺処分することがないよう保健所に国が支援するべき。民間企業やボランティアへも支援し、命を粗末に扱わない。税金で動物を殺すのではなく、法律で動物を救える世の中にすべき。
(7)意見交換
 環境省の「ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査」について
環境省の「ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査」について
・法を施行しても守らないのではどうしようもない。指導するだけでは次もまたやるおそれがある。何とか防ぐ手立てを考えなければならないが、例えばチェックするための第三者機関を設けるなど環境省が検討していることはあるのか。また、オークション側は偽装を認めているのか。 ⇒(環境省)具体的なことは検討中。第三者のチェックは行政のコストもかかるので、改ざん防止に効果的な方法を今後検討する。オークション側から話は聞いているが、偽装を認める認めないの話はしていない。
・繁殖業者やブリーダーの所にいる獣医ははっきり言って信用できない。第三者の獣医を入れてほしい。コストがかかると思うが大事なこと。 ⇒(環境省)ご指摘のとおり、内輪の獣医が出生の証明書が書いているところが多いので、また内部で改ざんが行われないように対策を検討したい。
・本来愛護法を違反している業者に対しては、動物愛護法の法文では「指導」という文言は見当たらず、「勧告・命令」ということになっている。今回の調査では、ほとんど口頭指導や文書での指導になっているが、「指導」をする法的な根拠は何か。 ⇒(環境省)口頭指導についてはご指摘のとおり法的な根拠はない。今後厳しい指導になっていくかは別問題。違反の内容をふまえて自治体で指導していくその途中経過と認識している。
・勧告に進んでいるのが2件しかない。こういったことに対して行政がきちんと運用できていないと思うが、それについてどう考えているのか。
また、動物の法律というのは動物愛護法しかなく、畜産動物や実験動物についても守っていかなくてはいけない。これは国連やOECDなどあらゆる国際機関が今どんどん進めていることで、近隣諸国も法律を作っているなか日本にはないという状況。動物愛護法をもっと大きく広くとらえて経済の問題まで含めて発展させていくということで、ぜひ次期法改正は大きな1歩を進んでいただきたい。
⇒(環境省)今後、動物愛護法の改正PTにおいて対応していきます。
・口頭指導は各自治体記録に残っているのか。
⇒(環境省)きちんと記録に残しているのかについては確認していない。指導をしたという報告は受けている。
 その他意見
その他意見
・ジャパンケネルクラブからの血統書をとる場合、私が知る限りだが、お金を出せばミックス×ミックス、ミックスがどんなに掛け合わされていても血統書が出る。消費者は血統書があるだけで買ってしまう傾向があり悪循環になっている。ジャパンケネルクラブに対する行政からの適切な指導や監視は行っているのか。 ⇒(環境省)指導していない。消費者や販売の話になるので、消費者庁の話になるかと。
・販売のために空路や陸路を使って非常に長い輸送をして売買の場に運ぶことに、距離の制限はかけていないのか。最近コマーシャルでも堂々とそれを謳って運搬してますよというのを見ると、絶対に規制をかけなければいけない。先日も記事になっていたが、能登から運ばれた鳥が輸送の翌日に亡くなったこともあり、輸送は動物に強いストレスがかかるので、しっかりとした議論が必要。
⇒(環境省)飼養管理基準では距離については決まっていないが、輸送時間はできる限り短くするように規定している。ご意見として頂戴する。
・(杉本彩)動物愛護法改正に向けてのアンケート結果に「生体販売の禁止」という意見がある。昔だったら世間から「生体販売の禁止」という言葉がトップに上がってくるようなことはなかった。これが出てきたということは、悪質な事業者の非道な虐待行為が事件化・顕在化していて、生体販売が問題の根源であることを国民の皆さんが十分ご理解されている証拠。生体販売の禁止はたしかにハードルが高いとは思う。せめてイギリスみたいに幼齢動物の売買の禁止が実現すれば、細かくいちいち規定していく必要もなくなり、大きく前進すると思う。せめて幼齢動物の販売禁止は、これだけ世の中が理解して支持しているわけなので、そろそろこの議論の場にあげていただきたい。
(8)閉会の挨拶(逢沢一郎議員)
いろんな角度からの質問や指摘をいただいた。この議連は名前のとおり「犬猫の殺処分ゼロを目指す」ということではあるが、非常に幅広く動物の愛護、アニマルウェルフェアの考え方の実効性を確保するという大きな目標も大事にしながら活動していきたい。
現場では見るに聞くに堪えないひどいことが実際に起きている、これは現実。法律があっても実効性を確保することが難しい。地方自治体の職員の数、体制に大きな課題があるのも事実。我々が努力する必要があり、各自治体にもしっかりと認識を持っていただく、そのことは今後も議連として強力に進めたい。
傍観しているだけでは議連の務めは果たせないので、しっかりと歩みを進めたい。次期法改正でどういうアジェンダをどう整理して、国民総意のなかでどう体制を作っていくか取り組んでまいりたい。議連のアンケート調査、環境省の調査はビッグデータとしてしっかり受け止め、読み込むということからスタートしていきたい。実りある議連を今後も進めたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
第6回 動物愛護法改正PT(2024.02.05)
(1)改正動物愛護法の施行状況について関係者ヒアリング(環境省)
①8週齢規制やマイクロチップ装着義務化、飼養管理基準省令の運用状況について
■8週齢規制について
動愛法改正に伴い、H25年から45日齢規制、H28から49日齢規制、R3から56日齢規制が導入された。
犬・猫を扱っているペットオークション業者、ブリーダーの動物愛護管理法の順守状況を確認するために都道府県、政令指定都市に対して一斉調査を依頼した。
現在、自治体ごとの調査結果の確認中。結果がまとまり次第公表する。
■マイクロチップについて
R4年6月施行。登録頭数は毎月平均5.3万頭ペースで増加。昨年9月には合計で100万頭。
現在は120万頭越え、犬:猫=7:3の割合で推移。
■マイクロチップに係る狂犬病予防法の特例制度への参加状況
特例制度に参加した自治体において、犬の登録または所有者変更があった場合に通知が自治体に飛んで、マイクロチップが犬の鑑札とみなされる。
施行後、2月1日時点で261自治体が参加(全市町村の15%)
■飼養管理基準省令の運用状況について
R3年に公布、同年6月に施行。経過措置を講じ、段階的に施行。
既存の動物取扱業者について基準全体が適用され始めたのは、R4年6月以降。
R3、R4年度の立入検査や勧告の件数を集計した結果、R2年度から増加。
- 動物取扱業者への立入検査件数
| R2年度 | 19,346件 |
| R3年度 | 21,250件 |
| R4年度 | 26,699件 |
- 勧告、措置命令及び登録取消命令の件数
| 勧告 | 措置命令 | 登録取消命令 | |
| R2年度 | 6件 | 2件 | 3件 |
| R3年度 | 12件 | 1件 | 2件 |
| R4年度 | 22件 | 1件 | 1件 |
②犬猫以外の動物に関する飼養管理基準省令制度に向けた進捗状況について
■犬猫以外についての飼養管理基準
哺乳類・爬虫類共通で作成方針を以下のとおり3つ検討中。
- 動愛法第21条動物の健康と安全の保持及び生活環境の保全上の支障の防止の観点から基準を設定する
- 基準は自治体の職員が現場の動取業者に対して守らせる基準になるので、自治体職員が順守状況を確認でき、明確に良い悪いの判断ができ、根拠を持って必要性を説明できるような基準にするなど自治体の現場での実用性を考慮する
- アニマルベースドメジャーの考え方を基本にして、動物にとってその行動や状態に着目した検討を進める
■犬猫以外の哺乳類の飼養管理状況
飼養管理上の課題を踏まえ、基準の項目ごとに下記のいずれかとすることを検討中。
- 犬猫の基準を参考に哺乳類全体へ適用する項目
- 犬猫以外の哺乳類を7グループに分類し、グループごとに適用する項目
- 現行の哺乳類・鳥類・爬虫類の共通基準をそのままとする項目
R6年度以降に哺乳類関係の基準を策定、基準の解説書を作成し、基準の細部解釈を周知予定。
■爬虫類関係の飼養管理基準の状況
実際の飼い方を調査中。R6年度以降、検討を継続する。
■鳥類の飼養管理状況
R7年度以降に検討予定。
③改正法附則及び委員会決議に盛り込まれた検討条項についての検討状況
改正動物愛護管理法 附則(第8条~第11条)の対応状況について、環境省や関係省庁で調査を行っており、結果が出次第、公表する。
④犬猫の殺処分数
R4年度の殺処分数は、合計約1万2000頭。うち犬2,400頭弱、猫9,400頭弱。
依然としてゼロではないがかなりの数減ってきている。
(2)改正動物愛護法の施行状況及び次期動物愛護管理法へ向けた主要な検討課題について関係者ヒアリング(PEACE 命の搾取ではなく尊厳を 東様)
■動物愛護法強化の影響力
畜産動物への暴行に対し、動物愛護法違反として検察が受理した件数や起訴された件数が顕著に増加。
2023年には、乳牛を暴行する様子を自ら撮影した酪農場従業員に有罪判決が下された。
ただし、業務の一環として虐待に当たる行為を行っている場合には、告発しても立件されない状況は続いている。
■2019年改正動物愛護法で未施行の部分
●犬猫以外の哺乳類、爬虫類、鳥類
爬虫類について、そもそもどのような基準になるか不明で、要望がしにくい状況。
順番に検討すると、追加されていくだけで全体にかかる部分の改正がなされないのでは。どの動物にも共通で見直しを。
●動物園の動物
日本動物園水族館協会の基準があるが、協会非加盟の施設に対して行政は指導ができるのか疑問。なんとなく除外されている雰囲気があるが、動物園の動物についても漏らさず、具体的な基準を定めて欲しい。
海外では、サーカスでの野生動物飼養を禁止している国が50か国を超えているなかで、日本は簡易飼育で業登録ができてしまう。コンテナ飼育が出来ないような基準を。
●繁殖・販売業者による劣悪飼育
犬や猫以外の動物も、繁殖・販売業者による劣悪飼育に苦しんでいる現状がある。犬猫の飼養管理基準と同じように基準を定めて欲しい。
鳥の足を拘束したり、野生動物に洋服を着せたり、ハーネスで動けないように固定し展示されている。
●室内動物園、アニマルカフェ
プレハブの建物に多数の動物を飼育するふれあい動物施設がある。ヤギやポニーを放飼場もない室内で飼育、展示している。
手洗いや消毒などの衛生管理も行われていない。⇒厚生労働省の「ふれあい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン」や農林水産省の「各畜種の飼養衛生管理基準」との整合性がとれていないのではないか。
絶滅危惧種として問題になっているカワウソのカフェもある。半水生なのに泳げる環境がない。このような飼育や展示を許す基準とするべきではない。
アニマルカフェは国際的に批判されていることを踏まえて欲しい。
●爬虫類
体がまっすぐになれないような小さな食品パックに入れられて売られている。
ドイツやイギリスなど海外の飼養設備の数値基準を参考に、数値を決定してほしい。 最低限体を伸ばせるようにしてほしい。
●犬猫の移動販売
新たに定められた飼育管理基準では「犬猫については輸送後2日間、健康状態を目視確認してから販売すること」が義務付けられ、実質的な移動販売禁止だと説明があったが、依然としてトラックの荷台に詰め込まれたままの夜間移動が自治体で許されている状況。
法改正で、固定の事業所住所以外の登録を禁止すること。イベント会場、駐車場、公園等では登録できないことを明記するべき。
●動物を殺す場合の方法について
改正動愛法第40条に「国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない」と盛り込まれたが、殺処分方法に関する指針に変更はなく改正が活かされていない。(自治体の炭酸ガスによる殺処分方法や意識喪失がないままの屠畜)
■附則について
- 動物取扱業・罰則の対象種の拡大⇒「すべての脊椎動物」とする(現在は両生類のみ)
- 動物取扱業の対象業種の拡大⇒動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業等を含める(現在は「畜産業者」が挙げられていない)
- 動物実験代替法の利用を義務化、3Rの徹底 ⇒動物実験の代替や実験動物数の削減を義務化、代替法の開発・普及を国の責務とする
■次期動愛法に盛り込むべき主要な課題(附則なし)
- 産業動物に関する条項を新設
- 輸送に関する条項を新設
- 自治体職員の「動物Gメン化」⇒虐待に対して、行政が積極的に迅速かつ着実に手続を遂行する制度を構築する。
- 飼育動物のホワイトリスト化⇒家畜化されていない野生由来動物を安易に飼う人が多すぎる。限定してほしい。
(3)意見交換
・最近フクロウカフェが増えている。足を括られて飛べない状態で展示・普段は隠れる場所にいるのに常に人から見られる。フクロウにとってはかなりストレスのかかる状況にいると思うが、現状どのような制限が設けられているのか?
⇒(環境省)第1種動物取扱業の展示業に該当。飼養管理基準を守らなければならないが、従わなければ段階的に自治体が対応している。
⇒(東様)飼養管理基準に「拘束展示してはならない」とあるから現状できないはず。そういった施設の数が多く、指導の手が回っていないのでは。
・前回の法改正で劣悪な環境で飼育する繁殖事業者が後を絶たず、様々な数値規制を設けたが、経過措置を講じて猶予を与えたのにもかかわらず、繁殖引退犬の譲渡先を検討せず、多くの頭数を一気に手放している業者が問題になっている。数値規制が完全施行される年に、きちんと対応しているのか行政で確認する必要があるのではないか。
マイクロチップも誕生日をごまかして登録している状況がある。きちんと法律が運用されているか後追いをしなければならないが、環境省の対応状況はどうか。
⇒(環境省)実施状況の調査をするなど対応をしたい。
・犬猫以外の哺乳類や爬虫類を取り扱っている事業所数は?
⇒(環境省)事業所数はカウントしていない。頭数は哺乳類で45万頭。
〈その他意見〉
・産業動物を動愛法以外の法律に規定すべきかについて、アニマルウェルフェアの推進法のようなものが業界にあるが、推進法は2年法にしかならない。良い飼育は継続すればよいが、悪い飼育については規制法の中できちんと規制すべき。ぜひ動物愛護管理法の中で検討してほしい。
・動愛法で産業動物も実験動物も対象になっているのに規制がない。産業動物に関する告発があってもうやむやにされてしまうのは、動愛法の中で規制がないから。牛や豚の屠畜施設では、牛の施設で3割、豚で7割が飲用水がないという調査結果もある。厚労省に取材したが「動物愛護法で規制されてないから、それ以上は厳しく出来ない」と言われた。
・立入検査が増えている割には、その後の勧告・措置命令・登録取消命令はほとんどない。「自治体職員の動物Gメン化」の実現を望んでいる。自治体職員が指導、改善させようとしていない。立入件数は増えていても指導どまりで、状況が改善されない。動物虐待事件が刑事告発しないとおさまらなくなっている。いくら良い法律を作っても改善しなかったら意味がない。どうすれば自治体職員が効果的に運用できるかという問題を解決すべき。
・獣医師として虐待の相談を受けているが、その後は自治体に対応をお願いしている。「犬猫以外の動物は基準がないから対応しにくい」「不適正飼養管理が具体的に何かよく分からない」と自治体から言われる。不適切な飼養管理、動物虐待とは何かを動愛法に具体的に規定すべき。
(4)環境省よりマイクロチップ装着事業に関する進捗状況の報告
前回の報告から進捗なし。
第5回 動物愛護法改正PT(2024.01.22)
(1)「緊急一時保護」「飼育禁止命令」について関係者ヒアリング:
①運用面での課題について(警察庁・小野寺様)
- 令和4年(2022年)動物虐待事犯については、166事件、187人を検挙。令和3年(2021年)と比較しほぼ同数。令和2年(2020年)の動物愛護法改正により、動物虐待罰則強化を背景として、動物愛護に関する国民の関心が高まっている、という事もあり、近年は検挙事件数が増加傾向にある。
- 警察庁では、動物虐待事犯について、都道府県警察に対し迅速な捜査による被疑者の検挙を要請している。
- 自治体の動物愛護管理部局との連携の強化を指示すると共に、環境省が策定した動物虐待等に対するガイドラインを周知するなど、適切な対応を指示している。
■「緊急一時保護」等について運用面での課題
- 警察としては、所有者が判明しない犬猫、負傷動物等が拾得された場合、一時的に預かるという事はあるが、動物を継続的に飼養できる施設や、動物について専門的知識を有する人員などは有しておらず、虐待された動物を預かることは想定していない。
- 動物虐待衰弱等のレベルの判断も専門知識を有していない。
②英国の緊急一時保護制度について((公社)日本動物福祉協会・獣医師 町屋様)
(※英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)国際部長 Paul Littlefair氏からヒアリング)
■緊急一時保護の法的根拠:動物福祉法2006
緊急一時保護の制度に関しては、動物福祉法2006に明記されている。
- 獣医師の判断のもとで査察官や警察が保護できる。
- 例外的に獣医師を待つことが現実的でなく緊急的に保護が必要な場合は、査察官や警察の判断で押収できる。
つまり、所有権に関わらず緊急一時保護が可能。
しかし、裁判で有罪にならない限り没収(所有権の剥奪)はできない。無罪の場合は、返還。
■英国での一般的な虐待対応の流れ
国民からの相談苦情等は、RSPCAナショナルコールセンターに集約。相談内容により対応部署が変わる。例えば・・・
- 「犬が放浪していた」「怪我をしていた」⇒アニマル(ドッグ)ウォーデンへ(地方行政機関)
- 飼養方法など簡単な内容⇒コールセンター職員が対応
- 動物の救助や虐待疑い相談の場合(平易な案件)⇒アニマルレスキューオフィサーが対応
- 動物の救助や虐待疑い相談の場合(深刻な案件)⇒RSPCA査察官が現場対応
■RSPCA査察官が対応した場合の流れ
- 詳細情報の確認(いつ、どこで、誰が、何を、どうしたかなどの情報確認、以前査察に入ったか、電話内容が正確かどうか等)
- 査察計画
- 現場訪問
- 動物の状態を確認(訪問した際に中に入ることを拒否された場合は、玄関先に連れてきてもらい必ず動物の状態を確認する)
- 飼養環境を確認
査察した約6割は問題ない、もしくは簡単な助言で解決するが、やや深刻な事案については「動物福祉評価表(Animal welfare assessment form)」を使用し、より深刻な事案については「動物福祉警告票(Animal welfare assessment WARNING NOTICE)」を使用し改善を促す。
- 評価表及び警告票に基づいて改善されているかの確認の為、1週間以内に再訪問。
- 非常に深刻な問題については、動物はただちに緊急保護され、所有者は法に基づき起訴される。
RSPCA査察官には法的権限がないため、強制立ち入りや緊急保護が必要と判断した場合は、警察と協働する。そのため、RSPCAと警察は事前に協働協定を締結している。
■虐待等の主な評価方法
虐待をどう評価しているかは、動物福祉法2006の第9条に5つの自由を発展させた動物の5つのニーズが明記されている。これらがしっかり満たされているかどうかが、最初の評価ポイントとなる。
- 動物の5つのニーズ(第9条)
(a)適切な環境に対するニーズ
(b)適切な食事に対するニーズ
(c)正常な行動パターンを示すことができることへのニーズ
(d)他の動物と共に、又は他の動物から離れて飼育される事へのニーズ
(e)痛み、苦しみ、怪我、病気から保護されることへのニーズ
動物虐待についても第4条に「不必要な苦痛を与えること」とある。
- 苦痛の立証⇒獣医師による証言
- 不必要の立証⇒獣医師のほか、司法関係者等からの証言
■保護した動物の移動・保管について
- 保護した時に飼養されていた場所、または適切と考える他の場所。
英国には、大規模な保護団体があり、多くはそこに収容される。
行政や警察の収容スペースがあっても小さいので、通常、警察や行政で一時保護したとしても、その後、民間団体に保護依頼がある。
出来る限り速やかに動物を安全な場所に移動させる。特に死体があった場合はすぐに移動させる。つまり、基本は安全な場所への移動が最優先。
馬などの大型動物の場合など、すぐに移動できないケースは、飼われていた場所で民間団体のスタッフがその場で世話をすることもある。その際、トリアージをして状態の悪い個体から移動する。
●緊急一時保護の問題点は?
⇒保管場所の確保。そのため、平時から他機関や他団体との連携など準備をすることが重要。
●緊急一時保護と同時に所有権も奪えるのか?
⇒奪うことはできない。有罪が確定した場合は所有権を剝奪できる。(動物福祉法2006 第33条)
●虐待疑いの現場への立ち入りや、真夏に鍵がかけられた車内等に放置された動物を発見した場合の対応は?
⇒強制的に立入りをする場合は、警察官と(法律上の)査察官は司法機関に令状を得て実施。
所有者の財産を壊さなければ救助できない場合は、基本的に警察が対応。
警察の到着まで間に合わない緊急を要する場合は、警察に電話で車等の窓を壊してレスキューする旨を必ず伝えて了承を得て実施する。
(2)意見交換
・動物は、証拠物としての押収となるのか?
⇒(町屋様)英国では証拠品としての押収となる。
・立入を拒んでいる飼い主にも動物を玄関口まで連れてきてもらう、という事だったが、それは査察官のコミュニケーションによって可能にしているのか、警察と一緒に行っているから飼い主も最終的には断れないのか?
⇒(町屋様)最初の訪問は警察とはいかない。本当に虐待なのかどうかという判断をするための訪問だから。行って虐待かどうか判断するためには、被害にあっているという動物をしっかり見ることが最優先事項。室内に入れなくても動物をみせてくれ、と必ず言う。それでも断られるようなら警察と共同で立ち入りをする。
・保護した動物を民間に預けるときの費用はどうしているのか?
⇒(町屋様)費用に関しては、ほとんどRSPCAで賄ってしまう。有罪になった場合、経費に関して請求できるが、ケースバイケースだがRSPCAはほとんどしていない。無罪になったら請求することはできない。
・虐待者である所有者を排除することはできるのか?
⇒(町屋様)その場で世話をする場合は、所有者は身柄を確保されているか、虐待で訴えられていることが多いのでその場にいないし、法律で「保護した時に飼養されていた場所で飼養管理できる」と決められているから、中に入らないようにできるのではないか。
・家宅捜索に入った時点で、所有権放棄させて、そのままセンターに収容すればかなり問題が解決する。勿論法律改正をどうするか、ですが、環境省が各県、動愛センターに『家宅捜索時に所有権放棄をさせて収容することをスムーズにやって欲しい』と徹底するのはどうか。
⇒(環境省)虐待事案に際して必要に応じて所有権放棄を働きかけるというのは環境省の虐待ガイドラインの中には明記がある。
環境省が自治体に研修する際にも、所有権の壁で、現に被虐待動物が虐待者の元にいる訳ですから、その状態を脱するためにも必要に応じて、所有権放棄を働きかけていきましょう、ということは常に言っている。ただ、所有権放棄は相手の同意があっての事なのでスムーズにいかない事例もある事は聞いている。
<その他意見>
・日本の場合は、沢山虐待されている動物がいるのに、ごく一部だけを裁判で有罪にするというケースばかりなので、全ての動物を救うには裁判の没収言い渡しでは無理だと思うので、飼育禁止命令が必要だと思っている。
・家宅捜索時に動物たちが虐待されている状態にあるかを確認することは、その後の処罰に関わってくる。家宅捜索時に獣医師・動愛センター共に同行するよう、全案件で徹底すべき。
・行政が適切に虐待を判断してくれない。行政が「やらなくはいけない」と法律を書き換えてほしい。罰則も付けてほしい。行政を厳格に運用していくところにより注力してほしい。
・ドイツでは、動物福祉をしっかり学んだ者が動物福祉に特化した公務員獣医になる制度。
研修できる機関の構築が必要。
(3)環境省よりマイクロチップ進捗状況の報告
2023年12月22日に政令を改正。令和6年4月1日からマイクロチップの手数料を改訂。
電子の申請に関しては300円を400円というような改訂となる。
第4回 動物愛護法改正PT(2023.11.08)
(1)総則的規定_第1条(目的)第2条(基本原則)第7条(動物の所有者又は占有者の責務等)について課題や要望について関係者ヒアリング
■島弁護士:「動物福祉」の文言を加えるべき。下線②を「動物の福祉の向上を促進するとともに」とする。
■JAVA和崎様:動物福祉とは何かを明確にし、下線①を「国民の間に動物福祉を守る倫理的責任を根付かせ」に変更する。
(基本原則)
第二条 動物が①命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、②人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
■島弁護士:「人にとっての利益」という文言を入れるべき。下線②を「人と動物の共生する社会の実現が人にとっての利益でもあること」とする。
■JAVA和崎様:
・「5つの自由」を盛り込む。すでに「飢えと渇きからの自由」「肉体的苦痛と不快からの自由」「外傷や疾病からの自由」に相当する文言は現行法に記されているので、残りの「恐怖や抑圧からの自由」「正常な行動ができる自由」を追加するべき。
・下線①「命あるもの」を「命あるもの、苦痛を感じるもの」とする。「命あるもの」だけでは、動物をただ生かしておけばよいとも受け取られかねず、「苦痛を感じるもの」も並列すべきである。
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、①その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、②当該基準によるものとする。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その③予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、④繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
■JAVA和崎様:
・下線②を「当該基準を遵守しなければならない」と改める。
・下線①「適正飼養」と④「繁殖制限」を「しなければならない」と改める。
・下線③「疾病の予防」は「予防に努めなければならない」とする。
適正飼養・繁殖制限・疾病の予防は、動物を飼養する上で当然のことであるにもかかわらず、違反が後を絶たない。義務とすることで、行政の指導がしやすくなり、指導の徹底と確実な改善のため、遵守を義務化する必要がある。
・第7項の基準に、自治体の収容状況を改善するため、自治体の収容施設に係る全国一律の技術的基準を定め、加える。
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
■JAVA和崎様:
・「動物販売業者の責務」の対象を、販売業者だけではなく動物を譲渡する者全般に拡大する。安易に動物を譲渡してしまう自治体、愛護団体、個人もいるため。
・「動物を譲渡す者は、譲受ける者が適正飼養できることを確認すること」と義務付ける。生き物を安易にプレゼントするイベントがあるため、不適切という事を示す必要がある。また、譲渡については現行法に規定がないため、追加が必要。
・飼養動物のホワイトリスト制を導入し、飼育してよい動物を指定し、それ以外の動物を飼養不可とする。家畜化されていない野生由来動物の飼育は不適切であるため。
(2)意見交換
- アニマルウェルフェア(動物福祉)、5つの自由の文言を入れることはマストだと思う。アニマルウェルフェアは今年の7月に農林水産省が畜産動物の国の指針を作った。動物福祉・5つの自由が未だに日本の法律に存在しないというのは余りにも遅れている。
- 第7条の所を「義務」にすることによって、所有者・占有者の責務が定められているにも関わらず、その責務を果たしていないような飼い主があっていいのかとなり、恐らく飼育禁止命令に繋がっていくのではないか。
- 動物愛護法2条1項で「人にとっての利益」というものを入れるという件、これは入れても入れなくても大幅に変わらないと思っている。1条の所でもう既に「人と動物の共生する社会の実現」というのが「人の為の利益」という事ははっきりしているから。
- 第7条4項「終生飼養」が謳われているところだが、その例外として適切な飼養ができない場合は速やかに新しい飼い主を探すことも飼い主の責任である、という「終生飼養の除外規定」を置くことも必要。
第7項の基準のところ、家庭動物だけではなくて、産業動物、展示動物、実験動物の基準も作られているが、動物福祉に配慮した内容に一切なっていない。これらの内容についてもしっかりと見直していく。特に産業動物に関しては、農水がアニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理基準を作成しているので、そういったものと連動させる。展示動物は、日本動物園水族館協会が、世界基準の動物福祉基準というものを作成している。そいういったものを参考にして作られるといい。
緊急一時保護を盛り込む際は、第十条の除外規定を撤廃することは絶対お願いしたい。昨年不起訴になったが、愛媛県で豚が農場で飢えて死んでしまった件や、今年島根県の農場で労働者が牛の虐待をしていた動画が出回った。茨城県の畜産動物センターでも長年、牛たちを従業員(準公務員)が殴る蹴るの虐待をしていた。結局、畜産動物も実験動物も、保護される規定がないことが問題なので。
(3)次回PTについて
「緊急一時保護制度」及び「飼育禁止命令」導入に関して警察庁、地方自治体から運用面の課題等についてのヒアリング及び、諸外国の事例について。
(4)環境省より報告
10月30日からマイクロチップに関する手数料についてのパブリックコメントを開始している。詳細についてはHPをご確認頂きたい。
■動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
民法における動物の位置づけ(明治大学法学部[フランス法・民法] 吉井啓子教授)
1. 旧来の「物」概念ではとらえきれない動物の性質
- 法の世界で「物」であるということは、人間の所有の客体、経済的、財産的価値を備えて譲渡可能である、というのが「物」の前提になっているが、現代社会において、動物は、経済的・財産的価値だけでは測る事のできない、人格的・感情的価値を有する存在として、普通の「物」とは違う存在になっている。
- 動物愛護管理法では、動物の所有者には「適正飼養と終生飼養の責任」が科せれているほか(7条)、所有者であっても「動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないよう」にしなければならず(2条)、違反すれば動物虐待罪として罰せられる(44条)と規定されている。 民法で言う所有権は、自分が所有している物を自由に使用・収益・処分できるとなっているが、その前提とは異なっている。
- しかし、民法上、動物は人の権利の客体となる「物」であり、その他の無生物と同様に「動産」のままである。
- 現代社会において新たな性質を有するに至った動物をどのように民法の中で位置づけるべきかに関する議論は我が国ではまだまだ少ない。機が熟していない段階である。
2. フランスにおける議論
- 農業海洋漁業法典L.214-1条以下に動物保護に関する規定がある。
農業海洋漁業法典L.214-1条
すべての動物は感受性(感覚)ある存在であり、その所有者によって、その動物の種類の生物学的要請に適合した条件の下で飼育されなければならない。
- また他のヨーロッパの国より少し遅れて、2015年に民法典に動物の法的地位に関する条文が明記された。
民法典515-14条
動物は、感受性(感覚)を備えた生命ある存在である。動物の保護に関する法律を留保して、動物は財産に関する制度に従う。
- フランスは「動物は物ではない」とまでは言い切っておらず、動物は「財産(物)」のままではあるが、生命があり感受性を有する点で他の無生物とは異なる「特別な財産(物)」としている。
- 民法学者からは様々な批判があったが「法は文化の産物であり、社会が動物に与える苦痛を制限する方向に進んでいるならば、動物保護の出発点である感受性を備えているという動物の性質を民法典にも明記すべきじゃないか」との反論が強くなされた。
- ドイツ、スイス、オーストリアなどは「動物は物ではない」とする一方、その後に、反対規定がない限り、物に適応される条文が動物に適応されるんだ。といっているので、結局物に関する民法の条文が動物に適応される、という点では、フランスやドイツなども変わらない、という事になる。
- 動物への法人格付与に関する議論もあり、動物法の権威であるマルゲノー教授らにより「自然人」「法人」に次ぐ第三の「人」として動物に法人格を認めて「動物人」とすることの提案もある。
- フランスは、古典的な民法の「人/物」を峻別する考え方に立脚しつつ、経済的・財産的価値でのみ把握される他の物とは異なる「特別な物」として動物を位置づけることを選択しているが、このような道を日本も選択するとすれば、他の「物」とは異なる動物の特別な性質をどのように民法に規定するかが問題になる。フランスではそれをL.214-1条から取っている訳だが、日本だと動物愛護管理法2条「命あるもの」と言った事になるのかと思う。
どうすれば虐待動物を救済できるか?民法が前提とする「人/物」二元論と権利主体としての動物(日本女子大学 細川幸一教授)
吉井先生から「自然人」「法人」に次ぐ第3の「人」として動物を位置付けるか、という議論がフランスである、というお話しがあったが、日本では今、第2の「法人」として動物を位置付ける、という議論がありそれについてご紹介したい。
1.動物愛護管理法における動物の位置づけ
- ご承知の通り、動物殺傷罪は刑法の器物損害罪よりも重い罪となっている。これは何故か?刑法上動物は器物であり、動物愛護管理法上動物は命あるものだから...これも少し曖昧である。何故なら、動物愛護管理法 第一条の目的規定では「動物を愛護する気風を招来し」となっており動物ではなく、気風を守ることが法益となっている。あくまでも動物保護、というのは人間の為にやるんだ、というところから抜けて出せていない。
- 国会の質疑でも串田議員から「動物虐待罪が保護する法益は何か」という質問に対し大森恵子環境省大臣官房審議官から「動物愛護の気風という社会の良俗の保護である」との回答があった。動物愛護管理法という法律が出来ているのに、動物に焦点があたっていない、というのが問題。
2. 民法における動物と動物法人の議論
- 日本の民法が前提とする「人/物」の二元論を維持する限り、世界は権利主体たる人と権利客体からなる物から成り立っているので、動物が権利主体になるためには、動物は物であってはならない。自然人か法人でなければならない。自然人が定義上ヒトしか指さないとすると、動物が法律上の「人」たり得るためには、動物を「法人」にすることしかない。
- 民法学の権威でもある小粥太郎教授や川上正二教授も動物を法人と構成することに一定の意義がありうることを認めている。
- 国会でも、政府に対し、動物が救済されない問題を指摘されていたが、この辺りに可能性があるのではないか。直ぐに実現できるとは思わないが、是非こういった議論を深化させていってほしい。
(2)国会図書館からのヒアリング
動物の法的な位置づけについて、諸外国の事例について説明をいただく。
1.動物は「物」ではないと法令で規定している国の事例
| 国 | 規定内容 |
|---|---|
| ドイツ | 動物は物ではない。動物は、特別の法律によって保護される。動物には、別段の定めがない限り、物について適用される諸規定が準用される。(ドイツ民法典第90a条) |
| オーストリア | 動物は物ではない。動物は、特別の法律によって保護される。物について適用される諸規定は、別段の定めがない場合のみ、動物にも準用される。(オーストリア民法典第285a条) |
| スイス | 動物は物ではない。動物に対して別段の定めがない限り、物について適用できる諸規定は、動物についても有効である。(スイス民法典第641a条第1項-第2項) |
| フランス | 動物は、感覚を備えた生命ある存在である。動物の保護に関する法律を留保して、動物は財に関する制度に従う。(フランス民法典第515-14条) |
2. 虐待されている動物を緊急保護できると法令で規定している国の事例
| 国 | 規定内容 |
|---|---|
| 英国 | ・検査官・警察官は、何らかの保護動物が苦しんでいると合理的に考えられる場合、その動物の苦しみを緩和するために、直ちに必要とみなした措置を講じることができる。 ・保護動物が苦しんでいる又は状況が変わらなければ苦しむことが見込まれると獣医師が証明する場合、検査官・警察官は当該動物を押収できる。例外的に、獣医師を待つことが現実的ではないほど押収を行う必要性が高い場合は、獣医師の証明は不要となる。 ・検査官・警察官は、①その敷地内に保護動物が存在し、かつ、②その動物が苦しんでいる又は状況が変わらなければ苦しむことが見込まれると合理的に考えられる場合には、保護動物の捜索及び押収等を目的として、敷地に立ち入ることができる。 (根拠法:2006年動物福祉法第18条、第19条) |
| スイス | ・動物が放置されていたり、全く不適切な条件で飼育されていることが判明した場合、所轄官庁は直ちに介入しなければならない。 ・所轄官庁は、予防措置として動物を押収し、動物飼養者の費用で適切な場所に収容することができる。必要な場合は、動物を売却するか安楽死させるよう手配しなければならない。 (根拠法:動物保護法第24条) |
| スウェーデン | ・動物が不当に苦痛を与えられており、監督機関の命令後もそれが是正されない場合等に、県中央行政庁は、動物を一時保護するよう決定しなければならない。 ・動物が苦痛を与えられており、かつ動物の苦痛が改善される見込みがないと判断される場合等には、県中央行政庁又はスウェーデン警察は、動物を即時一保護するよう決定しなければならない。 (動物保護法第9章第5条、第6条) |
| 米国(州) | ・動物を狭い乗物に閉じ込めて危険な状態にさらすことを禁止する又は乗物から苦しんでいる動物を救出した者に免責を認める法律を、31州が制定している。 ・このうち14州は、警察官・消防士等だけでなく全ての市民に対して、動物を救出する権利を認めているが、ほとんどの場合、救出前に「車内に強制的に侵入うる以外に救出手段がないことを確認する」「救急電話番号(911)又は地元の警察に通報する」といった手順を踏むよう要請している。 |
3. 動物虐待をした者から虐待された動物の所有権を剥奪すると法令で規定している国の事例
| 国 | 規定内容 |
|---|---|
| 英国 | ・動物虐待等により有罪判決を受けた者が、違反行為が行われた動物の所有者である場合、裁判所は、その者の当該動物に対する所有権を剥奪し、かつ、当該動物に対する措置を命じることができる。 (根拠法:2006年動物福祉法第33条) |
| ドイツ | ・合理的な理由なく動物を殺害する、動物に対して著しい痛み、苦しみ又は危害を与える等の違法行為に関連する動物は没収される。 (根拠法:動物保護法第19条) |
| フランス | ・飼い主が動物虐待で有罪判決を受けた場合、又は飼い主が見つからない場合には、裁判所は虐待された、又は遺棄された動物の処遇を決定する。裁判所は、当該動物の没収を宣言し、動物愛護団体に引き渡すことを命じる判決を下すことができる。 (根拠法:フランス刑法典第521-1条第6項) |
| 米国(アラスカ州) | ・裁判所は、虐待を受けた動物が、州又は当該動物に保護、世話、医療を提供している保管者に没収されることを求めることができる。 (根拠法:アラスカ州Stat. 11.61.140) |
4. 動物虐待をした者に今後の動物飼育を禁止すると法令で規定している国の事例
| 国 | 規定内容 |
|---|---|
| 英国 | ・動物虐待等により有罪判決を受けた者につき、裁判所は、動物全般又は特定種の動物の所有・飼育・取引・輸送等に関して、裁判所が適当と考える期間の資格剥奪命令を出すことができる。 (根拠法:2006年動物福祉法第34条) |
| ドイツ | ・合理的な理由なく動物を殺害する等の違法行為により有罪判決を受けた者等に対して、裁判所は、その者がさらに同様の違法行為を行うであろう危険が存在する場合には、動物全般又は特定の種類の動物につき、その保有、世話、取引、その他業として当該動物を扱うことを、1年以上5年以下の期間又は永久に禁止することができる。 (根拠法:動物保護法第20条) |
| スイス | ・動物保護法及び施行令に定める規定等に繰り返し又は重大な違反をして有罪判決を受けた者に対し、所轄官庁は、特定又は不特定の期間、動物の飼養、繁殖、取引等を禁止することができる。 (根拠法:動物保護法第23条) |
| スウェーデン | ・県中央行政庁は、動物を虐待した者等に対して、動物を管理することを禁止(動物禁止)するよう決定しなければならない。ただし、動物禁止を導く事情が他で繰り返されない可能性が高い場合には、動物禁止を決定してはならない。 ・動物禁止は、全ての動物種を対象とすることも又は単一若しくは複数のづ物種に対象を限定することもできる。動物禁止は、特定の数よりも多数の動物を管理することを対象とすることもできる。動物禁止は、一定の期間、又は当分の間適用うることができる。 (根拠法:動物保護法第9章第1条、第2条) |
| フランス | ・動物虐待で有罪になった者について、永久に、又は非永久的に動物を所持することを禁止する補充刑を科す。 (根拠法:フランス刑法典第521-1条第7項) |
| 米国(州) | ・2022年現在、20の州が、動物虐待で有罪判決を受けた者に対して、動物の所有を禁止している。この他、20の州、グアム、ワシントンD.C.では、動物虐待で有罪判決を受けた者に対して、裁判所の裁量で動物の所有を禁じることができる。 |
(3)意見交換
- 国会図書館の調査書によると、イギリスでは、動物の法的な位置づけがないまま、緊急保護ができる、所有権が剥奪できる、飼育を禁止できる、と全て出来ることになっているが、イギリスでの動物の法的主体性の議論はどうなっているのか?「物である」とか「物ではない」とかの議論がないままに、所有権を制限するとか、緊急保護する事を認めているのか?
- (国立国会図書館 調査室):「物とみなす」とか「みなさない」という議論はイギリスでは見られない。今現在、イギリスにはそういった規定はない。
- 民法を改正するのは困難だと思われているか?それとも、準用規定を設ければ民法改正はさほど難しいことではないと思われているか?
- (吉井先生):まだまだ民法の学会で議論されることも少なく、民法の中に「動物は物ではない」という規定を置くという段階ではないのではないか。「動物は物である」と規定していても、動物の保護を決してないがしろにしているものではなく「命あるもの」として、動物を保護する動愛法があるわけだから、人間側の義務を強化する方法で、動物愛護は進んでいくべきで「物ではない」という規定を置けば、それですべてが解決する訳ではないと思っている。
もし、民法に動物に関する条文を置くとすれば、フランスのように「動物は財産、物の範疇だが、他の物とは違う性質を有しているんだ」という事を規定するのがいいのではないか。
- そもそも動愛法が特別法として一般法より優先されるので、必ずしも物としての整理をしなくても、イギリスのように日本はやれる可能性があるのか?
- (吉井先生):動愛法で「動物は命あるもの」としているので、通常の「物、器物」とは違う扱いをする事は問題ないと考える。
- (細川先生):動愛法という範囲の中で、民法と他の法理で出来るのであれば、それは出来ますよね。クーリングオフなども同じ、これは、法理的にはあり得ないものだが、そこに立法事実があって、救済されない人がいるから、無条件解約権、という非常に強力なものを認めている。ある一定の範囲の中で、動愛法の理念の下で、命を救う必要がある、という所については、そういう立法をするというのはあってもいいのではないか。
- (細川先生):勿論、民法の改正は大変な話で、動愛法で出来ればいいが...
権利主張が出来ない弱者というのは世の中に沢山いるが、その人に代わって様々な事をやる制度がある。例えば未成年者に対する親権者、成年後見人、団体訴訟制度における適格消費者団体、彼らは、権利行使できない人に代わって権利を行使します。ここで重要なのは、弱者には権利があるという事です。動物には権利がないのに、人から財産物を奪って、守る、という事を内閣法制局がどう考えるのか、というのが一番気になっている。そこを上手く突破できないと、結局他人の物なんだから、という事に成り兼ねない。
民法改正は大変だけど、せめて「単なる物ではない」と規定し「従って、個別のものについては、特別法に委ねる」ぐらいのものがあればやりやすいと思うが、それもない中で、本当に動愛法で、他人の財物、権利の客体でしかない物を誰かがそれを奪って保護する、という事が上手くいくのか、と危惧している。
<Evaからの意見>
- 動物虐待をした者から虐待された動物の所有権を剥奪する場合の諸外国の法令をみると「有罪判決を受けた場合」などと規定されている国もあるが、処分が出るまでに時間が掛かるので、改正の際は、虐待者から速やかに動物を一時保護し所有権を停止又ははく奪できることを念頭に置いてほしい。
(4)動物愛護法改正PTの今後の検討・ヒアリング計画について
- 2023年10月:月1~2回のペースで関係者ヒアリング
- 2024年夏:ヒアリング終了~議員間討議で骨子案作成
- 2024年冬:骨子案提示~条文化作業
- 2025年5月:改正案を提出
第2回 動物愛護法改正PT(2023.09.19)
(1)衆議院環境調査室からのヒアリング:「所有権」について過去の国会での議論の説明
「動物の緊急一時保護に関する所有権の課題」に関して、これまでの国会での議論を整理して頂き、衆議院環境調査室にご報告頂いた。
- 劣悪環境下で虐待に遭っている動物の救済の必要性について
[第211回国会 参議院内閣委員会 令和5年5月9日]
(環境省)一般的には飼い主の意思をまず確認する必要はあるが、その動物に差し迫った危険がある場合などは、行政職員等が現場でその保護を行うことは現行上必ずしも否定されていない。したがって、個別具体の状況に応じて対応する。
- 警察官が暑い車中に閉じ込められた犬を救助した事例の法律上の根拠
[第211回国会 参議院環境委員会 令和5年4月25日]
(警察庁)一般論として、まずは車や犬の所有者への連絡を優先して適切な措置を講ずるよう促すこととなるが、連絡が取れなければ、動物愛護センター等の専門家と協力しながら、実際の状況に応じて、警察官職務執行法第4条第1項、第6条第1項(下記参照)に基づき、犬がいる車両に立入、犬に対する危害を防止するため必要な措置をとることもあり得る。
(避難等の措置)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
(立入)
第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
- 虐待をしているときには一時的に所有権を制限する内容の動愛法の改正を行う場合の法務省の協力の有無[第211回国会 参議院決算委員会 令和5年4月5日 ]
(法務省)一般論として、所有者は法令の範囲内で自由にその所有物の使用等をする権利を有するとされており、法令によって所有権を適切に制約することは可能である。動物の愛護管理の観点から、所有権に一定の制約を設けるべきかについては環境省において検討すべき事柄であるが、法務省としても必要な協力は行っていきたい。
- 虐待をしている場合には所有権を制限する法改正の検討の必要性
[第211回国会 参議院環境委員会 令和5年4月25]]
(環境大臣)所有権に一定の制約を設ける場合には、例えば飼育禁止を命じたり動物を没収したりする措置が考えられるが、こうした個人の権利の大きな制約については、憲法上の財産権(憲法第29条:下記参照)等々含めて、慎重な検討が求められる。今後の課題として、民事基本法制を所管する法務省の協力も得ながら、動物の飼育に係る飼育者の権利と義務の在り方に係る社会的な認識の把握に努めていきたい。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 動物を物と同じように扱う民法を改正する必要性
[第204回国会 衆議院法務委員会 令和3年3月10日]
(法務大臣)我が国の民法上は、一般に動物は物に含まれると考えている。民法上、動物を物と扱っていることを改めるとすると、その他の関係法令において、これをどのように扱うか、全般的な検討が必要になるので、影響が大きい。他方、動物を物として扱う制度自体は維持した上で、必要に応じて、その性質に応じた特別の規定を設けるなどの方法も考えれる。一般的に物としての扱いを改めることについては、その必要性も含めて、慎重に検討することが必要。
意見交換
- 法務大臣がいうように、民法上「動物を物」と扱っていることを改めるとすると、全般的な検討が必要になるので、制度は維持したまま、必要に応じて特別法(動愛法)でやっていく、というのは一つ参考になる。ただ「物ではない」という方向でも行けるかどうか議論できればと思う。
- ドイツの民法で「動物は物ではない」と定義されていて、他にオーストリアなどいくつかの国で定められている。動物の特性として「生命や感情がある」わけですが、その特性に反しない限りは、結局民法の「物」に関する規定を使う。また、その特性の部分に関しては、別途法律で動物保護法という形で決めて、そこに様々な保護のための規定を盛り込んでいる。
- 海外の法律を見ると、概念的に「動物は物ではない」という国としての姿勢を明らかにしているような感じを受ける。
- 「所有権を一時的に制限する事」に関しては、法令の範囲内で法務省もそれはOKとしているが「所有権をはく奪する事」に関しては、環境大臣も憲法第29条(財産権)を持ち出すなどしている。この点について専門家からの意見をお聞きしたい。
- 一時保護の議論もしなくてはいけないが、基本原則の目的規定(下記参照)が動けば他の条項も考え方が整理しやすくなると思う。その議論を先にしてもいいのではないか。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
<Evaからの意見>
- 緊急一時保護、所有権の一時停止が、仮に成立したとして、その先のことを不安視している。何故なら、行政が本当にこれを発令してくれるのかどうかという所だ。
先日も、銃刀法違反で逮捕されたドックトレーナーの男が、劣悪な環境で犬9頭を飼育していた。家の中には死骸(3頭)もあり、状態の悪い犬もいた。死骸があったら動愛法で完全にアウトにも関わらず、行政は「自然死かもしれないから虐待に当たらないかもしれない」と言ってそのまま死骸を放置した。(※その後、9月25日、動物の死骸を放置するなど劣悪な環境で犬を飼育した動物愛護法違反の疑いで逮捕)
一時保護の制度が成立しても、果たして適切に行政が発令してくれるのかどうか不安が残る。行政が適切に動いているかどうかの「監視」がそれを改善するのか、もしくは「民法」にまで手をつけることによって初めてそういったおかしな動きがなくなるのか。こういった点も視野に入れて検討頂ければと思う。
<関連意見>
- 自治体職員の規制を強化していく事を今回かなり重要視している。きちんと行政職員が動くという事を今回の法改正の中では実現したい。
まず最初にやるべきは、行政がずっと指導をし続けて次の勧告や命令にいかない、という大きな問題がある。一般の飼い主に対しても違反があったらその時点で勧告などに進まなくてはいけない、という義務化をする必要がある。
勧告、命令の期限を前回3カ月として頂いたが、3カ月だと動物は死んでしまう。1か月などより短い期間に変え、勧告したもののすべてが改善していなかったら必ず命令をしなくてはいけない、そういった改善がきでるようにと思っている。 - 行政の不作為、というのは悩ましい問題で簡単に改善されないと思う。一つ、行政手続法36条の3(下記参照)で「処分等の求め」というのがある。動物の場合、人権侵害があるわけではないので、なかなか不服申し立てもできないという問題点があるが「処分等の求め」というのは利害関係人である必要がないので、何か法律に反しているという事が見つかった場合に行政に対して処分を求める、という事が誰にでもできる。処分を義務付けるものではないが「処分を求める」という事を正式に法律上できる条文なので、これをどんどん生かしていく。事実上、強制力がないとしても仕向ける工夫をしていく事によっていろいろ改善されていく可能性があると思う。
第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
<その他意見>
- 動物愛護法の44条の第2項(下記参照)で「衰弱させること」が要件になっていてどんなに劣悪な環境に置かれていても衰弱させることが証明できないと、法律が構成できない、となってる。劣悪な環境にあるだけで犯罪が成立するよう訂正してほしい。「衰弱させること」というのが要件にはいっているので、因果関係まで証明させられ、証明できないと、犯罪が成立しないから、どんなに劣悪な環境を示しても、犯罪構成要件に該当しないといわれる。是非そこも検討していただきたい。
第六章 罰則
第四十四条 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(2)次回以降のPTで議論するテーマについて
- 所有権関連で、民法学者、憲法学者、法務省からのヒアリング。
- 行政での実効性をどう担保していくのか、自治体の現場職員、警察へのヒアリング。
- 各国で緊急一時保護や所有権の没収、飼育禁止命令をどのように規定しているのか、国立国会図書館に調査依頼。
上記いずれかで検討。
第1回 動物愛護法改正PT(2023.08.25)
(1)次期動物愛護法改正のためのPTヒアリング
次期改正に向けた論点項目に沿って「緊急一時保護制度の導入」「所有権の制限・動物の法的な位置づけの見直し」について各アドバイザーより報告を致しました。
Evaからも「緊急一時保護にまつわる課題」について事例を交え説明を致しました。
- 車内や室内の閉じ込めについては、熱中症や餓死等の緊急性を要す場合は速やかに保護できるようにすること。
- 虐待者に対しては、所有権を一時的に停止させる、或いははく奪できるようにすること。
それに加え虐待目的で購入する若しくはアニマルホーダー等の再犯を防ぐためにも、有期の飼養禁止命令を新設すること。 - どのような状態が緊急一時保護対象なのか明確な定義を設けること。
- 一時保護の方法としては、まず行政の動愛センターに入れ、事案の記録を取り必要な医療措置を行い、その後、適正な収容数及び飼養環境が確認できている登録団体に委託すること。
他のアドバイザーからも、
- 保護できるかどうかが現状警察の手腕に頼っている面がある。そうではなく、一律に保護でき所有権の移転も可能な制度の設立が必要。
- アメリカの州法など参考に出来るものはある。
- 権利を制限する場合は、それによって誰の権限や権利が保護されるのかを明確にする必要がある。その場合「動物の権利」というのは現実的ではない。しかし動愛法の目的である「人と動物が共生する社会の実現」が人にとっての利益なんだ、というふうに「人の利益」に結びつけて考えていく事もできるのではないか。
- 児童虐待の場合は、お子さんの生命・身体を守る、お子さんには当然人権があり人権享有主体(基本的人権が保障される主体)であるため、それが親権を制限する根拠となる。動物の場合、法律上は物であるため、保護法益(法によって守られるべき利益)の問題が出てくる。
- 動物を巡る所有権は、動物愛護法で自分で飼っている動物であってもみだりに殺傷できない、虐待できない、と規定されており、所有権の行使方法には、既に制限を掛けてきている状態。それをあと一歩推し進めていく必要がある。
- 所有権の制限のレベルも様々あると思っている。例えば、はく奪の場合は、動愛法違反で処罰の対象になった者、など規定を設けるべき。
などの意見がでました。引き続き議論を続けていく予定です。
(2)環境省より報告
日本獣医師快からのマイクロチップ装着事業に関する要請について
- 昨年の6月から指定登録機関(日本獣医師会)が運用を始めている。実際に必要な経費等を踏まえると指定登録機関自体が持続的に運営できる収支状況ではないという現状となっている。現在政令で手数料(オンライン申請300円・紙の申請1,000円)の額を定めているが見直しが必要になろうかと思っている。
- 現在は「環境大臣への登録」となっており、個人情報を環境大臣の下で管理する、という体制になっているが、国で情報管理をすると、日本獣医師会の方では使い勝手が悪い、という状況となっているので見直しをしてほしい、との話がある。解決策については環境省と獣医師会でまだ話し合っている途中である。
- (塩村議員)現在、国とAIPOの二重登録となっている状態。当然のことながら国へ登録をする人が増えているためAIPOが立ち行かなくなっている。では一元化すればいいのではないかと思うが、獣医師会曰く、迷子の犬猫の飼い主を獣医師が検索できなくなったため、AIPOは残していると聞いているが。⇒(環境省)令和5年6月に政令を変更し、負傷した犬猫や、迷子の犬猫は獣医師が検索をして飼い主に連絡できるようにした。
デジタル規制改革推進に関する、動物愛護法省令の見直しについて(進捗の報告)
- 8月4日、実証事業に係る事業者の募集が行われた。これは、代替できるデジタル技術の有無を公募により確認する趣旨であり、実証事業や規制の見直しに着手したものではない。
- 環境省としては、基準省令に基づく各飼養施設の保守点検の水準を維持する前提で対応している。
(3)その他
議連アンケート(次回動物愛護管理法改正に向けてのご意見、ご要望等のアンケート)の現状報告
- 7月28日からスタートし、現時点で1,500件届いている。大半は個人の方々からの意見。
9月末が締め切り。































![明治大学法学部[フランス法・民法] 吉井啓子教授](/_p/3649/images/pc/905d018e.jpg)